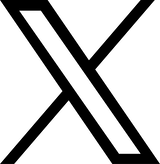私は浮気性の男だから、プリッツを食べたあと平気でポッキーも食べる
純愛は不可能だ。私は思い知った。純愛は夢物語だ。人間には不可能だ。コンビニで菓子を選んでいたときに気づいた。完全にわかってしまった。純愛など、ない。
昨日、コンビニでプリッツを買って食べた。塩味のプリッツだ。定番のものである。そして今日はポッキーに手を伸ばした。甘いものが食べたい気分だった。私は平然と日によって食べる菓子を変えている。昨日はプリッツ、今日はポッキー、明日はどうなる?
それは明日の気分しだいだが、たぶん、プリッツでもポッキーでもないだろう。自由に選ぶつもりだ。候補はいくらでもある。「細長い菓子」というふうに限定してみても、思いつくままに並べるだけで、プリッツ、ポッキー、トッポ、すこし趣向を変えてポテロング、じゃがりこなどを日々の気分によって選んでおり、さらにポッキーの中でも、チョコレート、いちご、抹茶、アーモンドのついているものも好きだし、そういえば、別会社のフランも好きだ。
浮気性。
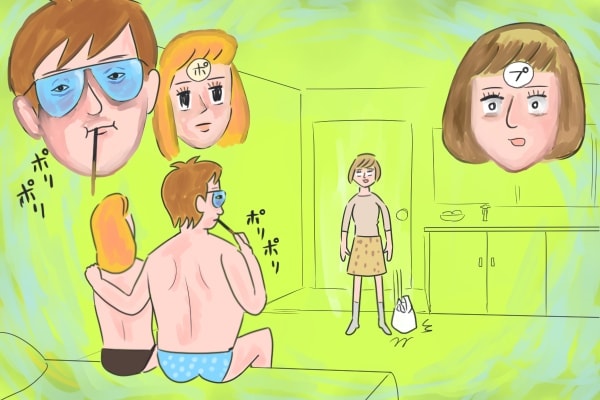
まごうことなき、浮気性なのだ。日々、あちこちの菓子に目移りしている。すさまじいペースで浮気を繰り返している。道徳を蹴飛ばしている。あまりに節操のない浮気ぶりには、神さまも目玉を飛び出すほどだ。
もちろん、こんなものは狂った理屈である。菓子は菓子でしかない。好きに食えばそれでいい。菓子との関係に純愛を求めてどうする。私も普段はそう考える。しかし、aikoをしこたま聴いた夜なんかに思うのだ。こんなことで、いいのだろうか。この日々のどこに、愛があるのだろうか。菓子だからといって、許されるのだろうか。
私は、プリッツに心がないことに甘えている。プリッツに自我がないとはこれ幸いと、翌日、隣のポッキーを平気で手に取っている。別の女とこっそり会うどころのさわぎではない。真横にいる。プリッツはポッキーの真横にいるのだ。浮気性のうえに無神経。まったく同情の余地がない。こんなものは、プリッツに心がないから成立しているだけだ。プリッツの塩味は、涙が乾いた後なのだと知らねばならない。
もしも、プリッツに心があって、理由を問われたとしたら、私はなんと答えるだろう? なぜ、平気でいろいろな菓子に浮気できるのか? プリッツだけを、ただプリッツだけを毎日食べる。なぜなら、プリッツのことが好きだから。そうした素朴で美しい世界観を、なぜ維持することができないのか?
プリッツは、塩にまみれた体のまま、すっと背筋をのばして、私に言うことだろう。
「あなたは昨日、塩味のプリッツが大好きだ、とおっしゃった。お酒を飲みながら、これが最高なんだ、とおっしゃった。わたしは、うれしかった。自分の塩味を、誇りに思えた。なのに今日、あなたはわたしに見向きもせず、隣のポッキーをお取りになった。わたしは、悲しかった。あの言葉は、嘘だったのですか? その場限りの、でまかせだったのですか? お酒が生み出した、軽薄なひと言だったのですか?」
私の体に、汗がにじむ。その汗は、罪の汗だ。罪が汗となって、分泌している。
「いやあ、それは」
もごもごと口を動かす。柔らかい綿を詰められたかのように、うまく言葉が出てこない。言い訳なのだ。今からはじまるのは、言い訳にすぎない。
「まあ、なんというか、いや、申し訳ないと思うし、自分でも本当にいやなんだけれども、ただ、これは理解してほしいことではあるというか、まあ、たしかに、わかりにくいことだとは自分でも思うんだけれども」
ああ、前置きが長い。罪人は、言葉をはぐらかす。本題に入るのが、怖いのだ。
「説明すると、なんだろうな、うまく言葉にならないけれど、要するに、人間の舌というのはね、わりと飽きやすいというかさ。昨日は、塩味のお菓子を食べて、すると今日は甘いお菓子が食べたくなる、とまあ、そんなふうにできているというかね。舌というのは、まあ、そういうもので、それは舌のないきみには、つまり、プリッツであるきみにはわからないことかもしれないけれど、そうなんだ。舌というのは、まあ、そういうものなんだよ。わからないかもしれないけれど、わかってほしい。僕も苦しいんだよ。しかし、舌はそういうものだから、仕方ない」
「そうやって、すぐ舌のせいにする」
プリッツは短く、それだけ言った。
その声は、ぞっとするほど冷たかった。
「じゃあ、舌はあなたではないのですか。舌だって、あなたの一部ではないのですか。なぜ、自分の舌のことを、他人事のように語るのですか。舌が他人ならよいです。それでもわたしが知りたいのは、舌に対する、あなたの気持ちなんです。あなたの舌がわたしを傷つけている現実を、どう思っているかなのです。あなたは、舌の言いなりなのですか。あなたは、舌の奴隷なのですか。そうでないなら、態度で示してほしい」
「いや、すごくわかる、ものすごくわかるし、傷つけてしまったのは申し訳ないんだけど、ただ、人間とは一般的にそういうものであって」
「わたしは、人間と付き合っているんじゃない。わたしは、あなたと付き合っているんです」
プリッツは、私を見つめていた。
「一般論に、逃げないでほしい」
その言葉が、私の胸をえぐったのだ。悲しいほどに、私の心を撃ったのだ。そして私は決めた。舌のせいにするのは、もうやめる。人間だからと開き直るのも、もうやめる。そして毎日、プリッツだけを食べる。月、火、水、木、金、土、日。私の一週間は、プリッツとともにある。浮気はしない。ポッキーは忘れた。ほかの細長い菓子のことも忘れた。塩味のプリッツだけが、私の恋人だ。
しばらく、幸福な日々が続いた。それは穏やかで静かな幸福だった。過去の私は非道であった。しかし今や、私は愛の申し子だ。季節が変わり、花が散り、万物が流転する間も、私の心だけは変わらない。愛とは永遠の別名だ。私は、プリッツを愛している。
しかし、徐々にプリッツの表情は変わりはじめる。悲しみの影が差しはじめる。私もまた、気づいていた。衰弱していた。私の体は、あきらかに衰弱していたのだ。手が震える。不意によろける。めまいで倒れ、嘔吐する。気づきたくなかった。しかし気づいていた。原因は明らかだった。
塩分過多。
私は、塩味のプリッツを食べ続けていた。もはや菓子だけでなく、朝昼晩、あらゆる食卓にプリッツが並んでいた。これが愛だ、これこそが愛なのだと自分に言い聞かせていた。私はもう動けない。布団から起き上がることができない。
自宅の一室で寝たきりになった私を、プリッツが見つめていた。
「あなたは、わたしを愛してくださった。心底、愛してくださった。うれしかった。わたしは知っていました。だけども、止めなかった。わがままな女です。あなたの健康よりも、愛を選んでしまった。わたしは、この塩が憎い。どうして、わたしは塩まみれで生まれてきたのでしょう。塩なんて、なければよかったんだ」
「塩まみれだから、好きだったんだ」と私は言った。
「嘘だわ、嘘よ」とプリッツは叫んだ。
私の視界はすでに霞んでいた。まばゆいばかりの光が見える。終りのときが来るのだ。思えば短い人生だった。しかし人生の最期を、私は最愛の菓子とともに過ごしている。プリッツに後悔してほしくない。
「汝らは地の塩なり」と私は言った。
「マタイ伝5章13節」とプリッツが言った。
しばらく沈黙があった。周囲には物音ひとつしなかった。薄れゆく意識のなか、何かを決意したようなプリッツの声が聞こえた。
「シャワーを浴びてきます」
だめだ、と言えなかった。声が出ないのだ。行くな、浴びてはいけない、きみはシャワーを浴びてはいけない。それがきみにとって何を意味しているか、わかっていないはずがない。
しかし声が出ない。腕が上がらない。体が動かない。行ってはいけない。シャワーを浴びてはいけない!
永遠のように思えた時間の後、気がつくと隣にはすべての塩を洗い落としたプリッツが立っていて、私を見つめながら、寂しそうに微笑んでいた。プリッツはやさしく私の体にふれた。それは、悲しい感触だった。
「ねえ、わたし、ふやけてしまったわ」
こうして、私とプリッツは体を重ね合わせたまま、その場で息絶えることになり、その後は天国において永遠の名のもとに結ばれるのか、どうなのか、それはよくわからないが、そろそろ言っておきたいのは、私はいったいなんの話をしているのか、ということである。
なぜ、プリッツと2人でこの世を去ることになっているのか。本当に、まずは深呼吸して落ち着け。
(文:上田啓太、イラスト:室木おすし)
※この記事は2019年03月10日に公開されたものです