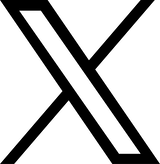外見40点の女が残念な美人に伝えたいこと
外見40点の女・薫がモテる理由を探ります。

地獄のなかで拷問を受けてるみたいな悪夢の合コンから5日後。私は昼休み、歯磨き中の薫を飲みに行こうと誘った。薫は化粧っ気のない、まあるい顔をキョトンとさせて、「土曜日に私と?」と言った。
そうだ、腰を据えて土曜の18時から尋問したいのだ。
薫はゴシゴシ歯を磨きながら、うれしそうに元気よく「うん! 行こう!」と答えた。口の端から飛んだ歯磨き粉がちょっと顔にかかったけど……、まあ気にしない。
当日。18時に大手町の適当な店で待ち合わせをしたのに、私はまだ駅の改札前にいる。いつも銀座と六本木に生息している由美が大手町の複雑な駅構内の罠にかかって、まだ待ち合わせ場所にたどり着かないのだ。
薫からはお店についたというLINEがきた。
ちょっと待っててね、と返す。由美を誘ったのは、薫とサシだとさすがに間がもたないと思ったから。大手町を選んだのは休日のこの街で知り合いに会わないだろうってのと、自分の家から電車1本で行けるから。お店はどこでもいいので薫に任せた。いつからか私は、相手との関係性や重要性に適した場所をチョイスするようになっている。最低かよ。
18時8分にやっと由美が到着。昨日と服が同じ。
「棚沢さんとこにいたの?」
「そう。えへへ。もうそのまま来ちゃった」
棚沢さんは、由美が大学生のころからダラダラと関係が続いてるおじさん。横浜で暮らす奥さんと別居していて、港区のタワーマンションにひとりで住んでいる。つまり不倫だ。
でも由美はそんなこと気にしていない。自由に遊ばせてくれて、奢ってくれる年上の男。別に棚沢さんだって若い女の子と遊べるんだから、お互いWin-Winな関係なんだろう。それに私もバーターとして高級ディナーを度々ご馳走してもらっているので、由美に説教なんてできるわけもない。
「男の家に泊まって夕方までだらだらするのダメなんだよ!?(マイナビウーマン調べ)」
「別にいいんだよ。棚じいだもん。あ、お泊りで思い出したけど、ラガーマンから連絡ないよう! いっそのこと、あの日お持ち帰りされとけばよかったかも」
由美はいいやつだ。エクセル全然使えないし、貸した漫画は絶対返さないどうしようもない女だけれど、それを全部チャラにするくらい容姿に華がある。さすが女子大のミスコンに出て準ミスに選ばれただけある。審査員に、君とグランプリの子の差は“教養の差”だと言われた由美。
由美の学部、教養学部なのに。
このエピソードなんか、もう最高。ああ、由美がバカでよかった。由美が派手なレースクイーンなら、私は清楚な女子アナだ。合コンは必ずセットで参加して“お好きなほうをお選びください”って身を差し出している。なのに、どうしてなんだろう。
もやもやした気持ちのままで18時15分。ガラガラ! と力任せに引き戸を引く。焼き鳥を焼くモワッとした煙の向こうから、あの女がこちらを見て手を振っている。

私の頭の中でゴングが鳴った。
休日の薫は、このガード下のしみったれた居酒屋に見事になじんでいる。いつものようにひっつめたポニーテール。大きめの白いTシャツに黒の半ズボンがぼんやりと体操服を連想させる。椅子の横には大きなリュックサックが置かれている。これから当てのない旅にでも出るのだろうか。
「遅いっ! もうビール飲んじゃってるよ?」
そばかすが目立つ化粧っ気のない顔をくしゃくしゃにして笑いながら、薫が着席を促す。
15分くらいの遅刻で先にビール呑んでいるのって、セオリーに反してる。相手が仕事でデートに少し遅れるとき、私は小説を読んで待つことに決めている。女の子がひとりでお酒を呑んでいるなんてはしたないし、だらだらスマホを見ながら待つのはなんだか知性がない気がする。そういうときの演出にいい仕事をしてくれるのが文庫本だ。退屈させていたのでは? という相手の気分も楽になるし、あとあれ。
清楚な女子が文庫本読んでる感じ、なんかすごく尊くない?
わかります? 小さな本をそっと両手に抱えて読んでるあの感じ。私が男なら、「もう、この子を一生大切にしよう」って思いますがね。どうなんですかね。
「なんかすごいお店だね……」
由美が珍しそうに店を見渡しながらつぶやく。カウンターには量産型のおじさんたちが隙間なく座っている。私と由美の登場に明らかな動揺が感じ取れる。
「このお店、私大好きなの! めっちゃおいしいよ。焼き鳥はヘルシーだし2人も大丈夫かなって思ったの。まずは2人ともビールかな?」
「ううん。私、ホッピーセット。黒で」
私は生粋のお酒好きだ。産まれも育ちも品川の由美にはこのお店は珍しいかもしれないが、私の育った田舎にはこんなお店が街中にあふれている。赤提灯のデパートだ。悔しいけど、こういうお店がめちゃくちゃおいしいことも知っている。
「あい子、この前の飲み会でホッピーなんか頼んでたっけ?」
「合コンで頼むわけないじゃん。だってそんなのモテないでしょう? 最初の乾杯からホッピーいくやつなんて。私、ちゃんと合コンの常識的なふるまいをしたのよ。なのにあの合コンは薫が全部持っていった。なに、あのヒミツのテクニック」
「そういうことね。前の合コンの話がしたかったのね」
「薫、モテモテだったじゃん。サッカー青年とはどうなったの? 連絡きた? もう会ったりしてるの?」
だめだ、問い詰め方がいきなり刑事だ。私としたことががっつきすぎ。
「サッカー青年? ああ、大橋さんね。おいしいチキン南蛮のお店見つけたから一緒に行こうって誘われたけど」
ああ。合コンのあと一生懸命チキン南蛮のおいしいお店を検索してるサッカー青年、もとい大橋の必死さに胸が締めつけられる。あたし完敗じゃん……。
「ぶっちゃけ、私も大橋さんのこと気になってたけど、大橋さんは薫のほうがいいみたいだね。付き合えるんじゃない? 結婚までいったらけっこう玉の輿だよ?」
やばい、言いながら泣きそう。急いで焼き鳥をかじってホッピーで流し込んだ。ほら、やっぱりリョータのときと同じじゃん……。
「ちょっと待ってよ、私、大橋さんのことなんとも思ってないよ。ていうか、あい子だって大橋さんと話してたっけ? 一回会っただけで、まともに会話もしてない相手を涙目になるほど気になるってどういうこと?」
薫の淀みのない瞳の中に、ホッピー片手のアホ面の私が映っている。薫のまっすぐな視線が私の心に問うている。
あっれ? なんであいつのこといいと思ったんだっけ?
たしか、ラガーマンは由美がホールドしてて、もうひとり(鳩)はあんまタイプじゃなかったから……。
自らも驚くほど無意識の消去法。
そう思った瞬間、私は一気に大橋のことがどうでもよくなった。苦悩の5日間を返してくれ、大橋。
「あい子は、大橋さんに“選ばれなかった”ことが悔しいだけでしょう?」
ビールをぐいっと呑んで薫は立て続けに言う。

「女はペットショップのチワワじゃないんだよ。小さいゲージの中で選ばれるのを潤んだ目で待つだけの人生なんてつまんないよ」
「カッコいい……」
初めての赤提灯に浮かれてロクに話も聞かずに焼き鳥を食べてた由美が思わずつぶやいた。
「ねえ、あのとき、本当はホッピー飲みたかったのにジントニック飲んでたの?」
薫がなだめるように哀れむように私を見て尋ねる。あれ? 薫からマザーテレサ的なものが出てる。なにこれ、慈悲?
「うん」
私は子どもがお母さんに甘えるようにコクンと頷いた。
だって学生のとき、サークルのかわいい女子が頼むのは決まってジントニックだった。だからそれに従っただけ。でも私はここだけの話、ジントニックをずっとこう思いながら5年間飲んできた。
ちょっとだけトイレの芳香剤っぽい味がすんだよなぁ……。
すきっ腹にホッピーが回ってきたのか、べらべらとそんなことまで話してしまった。

「もうさ、それ労働じゃん。」
「労働?」
「そう、やりたくもないことするなんて労働だから。あい子にとって合コンは労働なんだよ。しかも報酬が保障されてないやつ。やっとわかった! だからあい子、全然楽しそうに見えなかったんだ」
「合コンは私にとって労働……?」
次回、自分の捻じ曲がった価値観にメスを入れられたあい子が動き出します。
次の更新は8月3日(金)です。
1話「美人なのになぜかモテない女」
2話「合コンでヘルシーな料理を頼む女がモテない理由」
3話「外見40点の女でも男心をつかめる魔法の言葉」
(文:桑野好絵/マイナビウーマン編集部、イラスト:黒猫まな子)
※この記事は2018年07月27日に公開されたものです