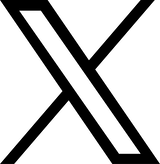くるり『ハローグッバイ』でよみがえる“左斜め上の恋”
聴く人、聴く環境によって「ラブソング」の捉え方はさまざま。そんなラブソングの裏側にある少し甘酸っぱいストーリーを毎回異なるライターがご紹介するこの連載。今回はライターの絶対に終電を逃さない女さんに「ラブソングのB面」を語っていただきます。

「僕のロッカー、君のロッカー 斜め向かいだった」
大学1年の夏、サークルの友人にCDを借りて初めて聴いたくるりの『ハローグッバイ』。慣れない東京での新生活に忙殺され、思い出す余裕もなかったことに気が付いた。左斜め上のロッカーだった彼のことを。
人生でただ一度きり「恋に落ちた」瞬間
高校に入学し、同じクラスになったのが出会いだった。
女子に「イケメン」と騒がれるタイプではなかったものの、さっぱりとした端正な顔立ちに、すらりとした長身。野球部所属で、普段つるんでいるのも部活の仲間。勉強にも熱心で、将来の夢は中学校の先生。趣味は釣りとパズドラ、好きな音楽はコブクロ。
一見どこにでもいる普通の少年ながら、どこかひょうひょうとした佇まいが独特だった。
「この人は何か特別なものを持っていそう」と気になりつつも、話しかけることも話しかけられることもないまま、6月になったある日の美術の授業。
美術室は自由席だったため、女子の仲良しグループに入れなかった私は、4人掛けの机に1人で座って黙々とデッサンを始めた。すると同じ机の向かいに彼が座ってきた。そして目が合い、彼はくしゃっと笑った。好きだ、と思った。
今この瞬間に私は恋に落ちたのだと自覚したのは、後にも先にもこの時だけだ。ちょっと優しくされただけで好きになってしまう陰キャ的な、そんな陳腐な理屈ではなかった。自分でもなぜなのか分からなかった。まるで催眠術にでもかけられたかのような、意思も理由もない恋だった。
クラスの教室に戻ると、彼のロッカーが私のロッカーの左斜め上だということに気が付いた。
私たちの教室には、教科書や体育のジャージなどを入れておくための正方形のロッカーが壁際に備え付けられていて、出席番号順に一人一つずつ割り当てられていた。
ここで言う「左斜め上」とは、横に3列あるうちの1番下の列だった私のロッカーから、上に二マス、左に一マス進んだ位置を指している。
そんなロッカーの位置だけで、彼に少し近付けたような気がした。
何よりも尊い彼の意志
それからというもの、私は彼の一挙一動を観察するようになった。やはり私の目に狂いはなく、彼は他の男子とは一味違った。
まず、地元でも特に田舎の地域から入学してきた彼の一人称は「ワシ」だった。他の男子は皆「俺」と言うなかで、彼は「ワシ」を貫き通していた。
クラスの目立つグループと仲が良い割に、誰とでも分け隔てなく接し、休み時間は一人で過ごしていることも多かった。
その一人の過ごし方というのも、風変わりだった。
例えばある日は、釣り竿を持って来て、千円札を付けた釣り糸を教室から廊下に垂らして扉を閉める。廊下を歩いてくる生徒が千円札を拾おうとしたところでリールを巻く、といった独創的な遊びだった。釣られた生徒を見て彼はケラケラ笑っていた。
ある日、彼が女子との会話で「甲子園に行きたいから恋愛なんてする暇ないし彼女とかいらん」と言っているのを耳にした。
別に付き合えなくてもよかった。彼がその意志を貫くことの方が、ずっと尊いことのように思えた。
田舎の自称進学校。おとなしく先生の言うことを聞いて、校則で決まっているわけでもないのにみんな同じような靴下を履いて、みんな同じような髪型と眉毛の剃り方をして、色恋沙汰の話ばかりしている。そんな狭い世界では、彼の言動から感じられる主体性や独創性が、とてつもなく輝いて見えたのだった。
美術の授業で絵の具を貸した。数学のテストで彼の誕生日と同じ数字が出た。ロッカーに教科書を取りに行くタイミングが重なった時に、夏服の袖と袖が触れた。そんな些細な出来事を拾い集めていた。彼の出席番号までもが愛おしかった。
私たちがクラスメイト以上の関係に発展することも、彼が甲子園の土を踏むこともなく、やがて別れの日がやって来た。
彼は地元の大学に、私は東京の大学に進学し、当然疎遠になった。
何でもないことを特別に感じる“恋”
『ハローグッバイ』を繰り返し聴いていると、ふと思った。
「斜め向かいのロッカー」は、何も特別なことではないのではないか。隣や向かいならまだ分かるが、おそらく「斜め向かい」は特に近いわけではない。
そう考えると、私にとっての左斜め上のロッカーも、比較的近くではあるものの、隣や上のロッカーの方が近い。何より、あの美術の授業以前は気にもとめなかった位置関係である。
そうか。きっと、何でもないようなロッカーの位置さえ特別なものに思えるのが恋なのだ。
振り返ればあの頃の私は、他にもほんの些細なことにいちいち共通点を見出したり運命を感じたりしていた。あらゆる何でもないようなことが特別に思えてしまうのが恋なのだと思った。
『ハローグッバイ』の歌詞はこう続く。
「いつからか あなたのこと忘れてしまいそう」
高校を卒業して6年。東京でいろんな人に出会って、いくつか恋愛もした。
地元の同級生とは疎遠になり、彼とも一度も会っていない。多分これからも会うことはないだろうし、彼は私のことを忘れているかもしれない。
それでも私は、『ハローグッバイ』を聴けばいつだってあのロッカーに戻れるのだ。
これから誰を好きになっても、彼は私の心の片隅で、あの時のように笑っているだろう。それも多分、心の左斜め上あたりで。
(文:絶対に終電を逃さない女、イラスト:オザキエミ)
※この記事は2020年04月30日に公開されたものです