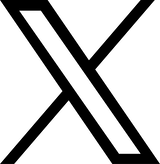名曲『サウダージ』に初めて共感した日 #ラブソングのB面
聴く人、聴く環境によって「ラブソング」の捉え方はさまざま。そんなラブソングの裏側にある少し甘酸っぱいストーリーを毎回異なるライターがご紹介するこの連載。今回はライターの生湯葉シホさんに「ラブソングのB面」を語っていただきます。
中学のころから大好きなバンドがいるのだけど、彼らのライブに恋人を連れて行ったことがない。というのも、私はそのバンドのことを親と同じくらい大切に思っているので、万一、ライブを観た恋人が「いまいちだったね」みたいなリアクションをしようものなら、その場でブチ切れてしまいかねないからだ。
大切だからこそ、触れられないところにしまっておきたい
理不尽なのはもちろん分かっているのだけど、私にとってそのバンドの存在はそのくらい大きくて絶対的なものだった。「10代で好きになったものはその人に一生ついてまわる」とはよくいうことだけれど、ワンマンライブも、お小遣いでCDをぜんぶ集めたのも、恥ずかしいけれど芸能人に本気で恋をしたのも、彼らが初めてだった。
だから、彼らのことをそれくらい特別だと感じるのは、自然なことだったんじゃないかと思う。
そして、ボーカルがライブのMCで「大切な人のことを思って聴いてください」と言うとき、私はいつも困ってしまった。だって「大切な人」と言われても、私にとってそれは、その曲をこれから演奏する“彼ら自身”に他ならないのだ。
彼らの歌うラブソングは、愛とか恋とか、自分自身に関する些末な出来事から一番遠い場所にあった。歌詞に共感することは、彼らが作った曲の世界を踏み荒らすみたいで嫌だった。目覚ましのアラームに設定している音楽をだんだん嫌いになっていくみたいに、自分の生活に彼らの曲を引き寄せることで、特別な曲たちを傷つけてしまいたくなかった。
“介助者”その言葉が隔てたもの
23歳、大学を出てライターのアルバイトを始めたばかりのころ、好きな人ができた。彼は同じ会社に勤めているカメラマンだった。
昼休み、彼はよく自分のカメラを持って会社の近所を散策していたから、私もたまにそれについていった。都内のビジネス街の真ん中に突如バグとして現れたみたいな、潰れかけのショッピングモールが私たちのお気に入り。目的もなくそのモールの中の100円ショップやらボタン屋やらを冷やかして、会社に戻るのが定番のルートだった。
一度、シャッターの降りた店の前に佇んでいた「たのしい運動会」という古いガチャガチャを二人で回したことがある。「お金がないから二人で一つだけ買おう」ということになって、玉入れや綱引き、徒競走のミニチュアの写真を見ながら、これかわいいね、これが出てほしいなと回したのだけど、出たのは「退場門」と書かれた白くて細い棒きれだった。
「ただの棒じゃん、最悪、全然楽しくねえ~」と涙が出るほど爆笑している彼を見て、あーこの人のこと好きだな、と思った。それで、どちらから好きと言ったのかは覚えていないけれど、私たちは付き合うことになった。
いろんなところにデートに行ったけれど、彼も私もとにかくお金がなかったから、多いのは公園だった。新宿御苑の芝生にブルーシートを敷いて、写真を撮ったりギターを弾いたり、それに合わせて歌ったりするのが好きだった。
彼は犬を見つけると、「あっ、ワンコロ」と言い、他のことそっちのけで犬にカメラを向けた。日が暮れてくるとカメラ屋を覗き、散歩して、屋台のラーメンを食べて帰る。無性に楽しくて、けれどこんな日常はずっとは続かないだろう、という予感だけが最初からあった。
メンタルの不調で彼の休職が決まり、私が彼の通院に付き添うようになったころから、私たちの関係は少しずつ変わっていった。
日中、仕事をしているとLINEがくる。気付かずに30分ほど放置していると、電話がかかってくる。慌てて会社の外からかけ直すと、電話に出た彼は一言目に必ず「ごめん、助けて」と言った。
躁と鬱を行き来する彼のことを、恋人としてできる限り支えたかった。けれど、LINEが1日に1000件きたりひどい暴言を吐かれたりするようになるにつれ、私も会社を休みがちになっていった。
ある日、彼と一緒に美術館に行って、お金を払おうとしたら「あ、手帳あるから無料で入れるよ」と止められた。彼の手帳を見た受付の人が「1名様とその介助者の方は無料です」と言ったとき、誰も悪いことをしていないのに、“介助者”という言葉に胸を刺されたような気分になった。
別れが引き寄せた名曲との再会
別れ話をしたのは1年後の春で、それも新宿だった。カレー屋で向かい合って座り、泣いてしまうから先に置いておこう、と隣のテーブルの箱ティッシュをつかんだ時点で涙が止まらなくなった。泣きながら「わか」まで言うと、彼は絶句し「店変えよう」とカレーをほとんど残してそこを出た。
私たちは何も喋らなかった。新宿に立ち止まって話せる場所は少なく、歩き続け、空車の多い駐車場をやっと見つけると車止めブロックの上に座った。大声で泣きながら「どうして好きなのにこんなことになっちゃったんだ」と悔しがる私に、彼は何度も「ごめん」と言った。
別れるという結論にお互いが納得するまで半日かかった。喫茶店やファミレスで大泣きして周囲の客にギョッとされては店を変え、3軒ハシゴし、最後に寄ったバルで彼は吹っ切れたように「よし、ここを出たらもう他人だ」と言った。

その帰りに歩いた新宿西口の景色をいまでも鮮明に覚えている。すっかり夜になった街はきらきら光っていた。なんでこんなまぶしいんだろう、と不思議だったけれど、泣きすぎてコンタクトレンズが片方落ちていたのだった。ぼやける視界の中で、横断歩道の向こうに見えるカラオケ館が信じられないくらいにきれいだった。私は人生でこんなにきれいな新宿を見ることはもうない、と思った。
改札前で別れてすぐ、涙でぐちゃぐちゃの顔をマスクとイヤホンで塞いだ。何でもいいから音楽が聴きたくて、iTunesでシャッフル再生したら最初に流れてきたのは大好きなバンドの曲だった。
「違う、こういうときには聴けない」と思って反射的に曲をスキップしようとしたのだけれど、その歌い出しでハッとし、指が動かなくなった。
私は私と、はぐれる訳にはいかないから
いつかまた逢いましょう。その日までサヨナラ恋心よ
誰のものでもない“私の”『サウダージ』
200万枚売れた『サウダージ』に、人生で初めて共感したのがそのときだった。私にとってポルノグラフィティは特別なバンドで、特にその歌詞を書いたギタリストにずっと憧れていて、だからこそ、曲を自分の恋愛に当てはめて泣くなんて失礼だと思っていた。
けれどその瞬間、ばかみたいだけれど、「ああ、私は私とはぐれる訳にはいかないんだ」と心から思ったのだ。山手線に乗り込んで、泣きながら『サウダージ』を何度も聴いた。
昔、ポルノのギタリストが雑誌に連載していたエッセイの中で、ファンの人に「サウダージを作ってくれてありがとう」と言われたのが忘れられない、と書いていたことがある。事務所のマネージャーに囲まれているメンバーたちに向かって、その人は少し遠くからそう言ったのだそうだ。
「曲がいつの間にか作った自分たちの手元を離れて、その人のものになることがある。そのときのために曲を作っている」と彼は綴っていた。ファンが言った「サウダージを作ってくれてありがとう」はきっと、「“私の”サウダージを作ってくれてありがとう」だったのだろう、と。
初めて読んだ10代のときは、その言葉の意味が分からなかった。けれどたしかにその瞬間、山手線の中で聴いた「サウダージ」は大好きなバンドの大好きな曲の一つではなく、“私の”曲だった。
(文:生湯葉シホ、イラスト:オザキエミ)
※この記事は2020年03月31日に公開されたものです