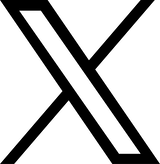宇多田ヒカル『First Love』とリンクする「初恋の記憶」
聴く人、聴く環境によって「ラブソング」の捉え方はさまざま。そんなラブソングの裏側にある少し甘酸っぱいストーリーを毎回異なるライターがご紹介するこの連載。今回はライターの琴子さんに「ラブソングのB面」を語っていただきます。

「宇多田ヒカルは天才だ」と彼はよく言っていた。
その言葉を思い出したのは、失恋してからそれまで全く音沙汰のなかった彼の結婚報告を受けた時だったと思う。馴染みのカフェで5年ぶりに向かい合って話を聞いていた私は、結婚を機にたばこをやめてから太ってしまったと笑う彼の話を聞きながら、「ああ、そういえばこんな笑い方をしていたっけな」とどこか冷静に目の前の彼を観察していた。
胸の奥に大事にしまいこんでいた当時の思い出が断片的に浮かんでは消えていく中で、彼の薬指に光るシルバーから目を離せずにいた。
背伸びした「初恋」
当時18歳だった私が恋をしていた彼は、4つ年上の大学生。それまでにもいくつか恋を経験してはいたけれど、そのどれもが比べ物にならないくらい私は彼に夢中だったと思う。
社交的で博識だった彼は、家と学校の往復をするだけの毎日を過ごす私にいろんなことを教えてくれた。手先も人間関係も不器用だった自分とは違い、なんでも器用にこなす彼の全てに憧れていたけれど、長い指を添えてたばこを吸う横顔を眺めるのは特に好きだった。
とにかく背伸びをしたかったあの頃の私は、彼が好きだという宇多田ヒカルの曲を何曲かプレイヤーに落とし込んだ。しかし、少女らしからぬ大人びた感性で男女の機微を歌い上げる彼女の曲は、あまりにも幼稚だった当時の私にはいまいち響かないものばかりで、特に印象には残っていなかった。けれど漠然と、きっとこういう曲が似合う人が彼の隣にふさわしい女性なのだろうと感じたのは覚えている。
最後のキスはタバコのflavorがした ニガくてせつない香り
わずか16歳だった宇多田ヒカルが書いた『First Love』の歌い出しである。たしかに天才としかいいようがない。イントロで切ないピアノのメロディーが流れ込む中、ドキッとするようなインパクトとともに、これから紡がれるであろう物語の方向性を一瞬で理解することができる。
「初恋」という単語が持つ、甘酸っぱくてどこか現実味のないおとぎ話のような可憐な響きを一掃し、生々しくリアルな輪郭と重みを感じさせるこの歌詞は、曲中で私が一番好きな部分だ。
優しく終わりに導いてくれるレクイエム
5年ぶりに再会した彼と別れて家に帰ったあと、自室でなんとなしに流したその曲は、奥底にしまい込んでいた痛覚を呼び覚ますには十分だった。無意識に塗り固めて封印していた感情が雪解けのように流れ出して、思わず笑ってしまった。「ああ、あの時の私がいる」そう思ったら、涙まで一緒に溢れてきてしまった。
こういった時に思い浮かぶのはどうしてか、取るに足らない思い出ばかりだったりするから不思議だ。あのカフェでいつも頼んでいたメニュー。コーヒーをブラックで飲めないのをからかわれていたこと。肌寒い夜によく貸してくれていたパーカーの手触り。真正面から見つめられるのが苦手で、いつも顔を逸らしてしまっていたこと。だから記憶の中の彼は横顔ばかりだったこと。今でも写真は見返せないこと。結婚したことと同じくらい、彼がもうたばこを吸っていないという事実がショックだったこと。
――イヤホンを通して聴く宇多田ヒカルのよく通る歌声は、5年前の劣等感にさいなまれてうまく彼と向き合うことのできなかった幼い自分と、それでも持ち合わせていた感情の全てで懸命に彼に恋をしていた自分と、そして今この時二度目の失恋に気づいてしまった自分をなだめるように流れていった。
You are always gonna be my love
いつか誰かとまた恋に落ちても
I’ll remember to love
You taught me how
You are always gonna be the one
今はまだ悲しい love song
新しい歌 うたえるまで
彼女の代表曲である『First Love』は、誰の中にもある「初恋」という、とっておきの物語の熱をその身に思い出させ、優しく終わりに導いてくれるレクイエムなのかもしれない。
「初恋」は『First Love』と共に
飽きるまで泣いたあの日から更に7年という月日が経った今現在、もうこの曲を聴いても胸は痛まない。「若かったな、必死だったな」と振り返ってくすぐったい気持ちになるだけだし、何より私自身も何度か新しい恋をした。今や十数年前は響かなかった宇多田ヒカルのさまざまな曲が刺さりまくるようになった立派な独身OLである。
時の流れは平等に残酷だ。幼かった私がずっと忘れたくないと泣きながら抱きしめた思い出たちも、時間の流れには逆らえない。繰り返し頭の中だけで反すうされた思い出は、いつしか事実から遠ざかりゆっくりと美化されていく。
あんなに好きだった彼の横顔も、今は薄靄がかかったように不鮮明だ。けれど、それでいいのだと思う。少しずつ忘れていっても、最後の最後まで、この曲を聴く度に、彼の唇から移ったたばこのほろ苦い味がかすかによみがえるのだろうと思う。
初めてではなかった。けれど間違いなく、彼と出会って自分は変わって、始まった。だからこの先何年経っても、「初恋」と聞かれれば私はきっと彼のことを思い出す。そうきれいなことばかりではない恋愛だったけれど、願わくばいつまでも特別なまま、心の奥底で眠り続けていてほしい。
(文:琴子、イラスト:オザキエミ)
※この記事は2021年09月08日に公開されたものです