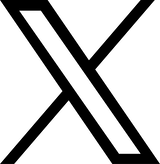「彼に奥さんがいるだけなのに!」第4話
30歳までに結婚したいのに、20代後半で不倫をはじめてしまったOL・原田櫻子。彼女の未来はどうなる? 恋と人生に悩む全女性に贈る、白井瑶さんのオリジナル小説連載。
【これまでのあらすじ】
職場の上司であり既婚者の観月壮亮と不倫関係を続ける、主人公・原田櫻子。禁断の恋に悩む櫻子を見て、大学時代からの友人・茉莉乃は「ほかの男性とデートすること」を勧める。デート相手として約束を取りつけたのは、大学時代に憧れていた先輩・高岡樹で……。
樹さんとの約束の日、わたしの足取りは重かった。不安と罪悪感で胸が痛い。3人で会う約束なのに、茉莉乃のドタキャンは決まっている。わたしのために仕組まれたデート。久しぶりに会う、しかも大学時代の憧れの存在だった先輩を、こんな茶番に付き合わせてもいいんだろうか。
……なんて思っているわりに、ちゃっかり新品のワンピを着ている自分にあきれる。
待ち合わせ時間ちょうどにお店の前につくと、うしろから声をかけられた。
「櫻子ちゃん?」
あの再会の衝撃を、なんて表現すればいいんだろう。お寿司を頼んだらステーキが来た、みたいな。推理小説かと思ったらバトルものだった、みたいな。スーツの似合う広告代理店勤務の先輩と会うはずが、めっちゃ個性的な抽象画を描きそうな……芸術家風の無精髭はやした男性? に、声をかけられた、みたいな??
「えーーっ、樹先輩ですか!」
「ひさしぶり! キレイになってて一瞬わからなかったよ」
いや、こっちはがっつり目が合った今も、ちょっと信じられないんですけど。とはいえ、人懐っこく笑った顔は大学時代のままだった。見ているほうの力が抜けてしまうような、ゆるやかでかわいらしい笑顔。この表情に、かつてわたしは恋をしていた。

大学卒業後に広告代理店で働いていた樹さんは、少し前に仕事を辞めたらしい。理由を聞いてもはぐらかされたが、次が決まっているわけでもないと言う。それでもまったく悲壮感なくNetflixのおすすめ映画を語る姿は樹さんらしいと言えば樹さんらしく、わたしを穏やかな気持ちにさせた。
「茉莉乃ちゃん、来れなくなったんだ。じゃあ櫻子ちゃんとデートだね」
こういうところも変わっていない。わたしは思わず苦笑した。
樹さんはいつでも誰にでもやさしい。周囲にかける言葉に嘘も下心もなくて、ついでに深い意味もない。彼にとって、そういった言葉は誰にでもばらまく大量生産品なのだ。それをオーダーメイドと勘ちがいする子があとをたたなくて、彼のまわりには女の子たちの情念が渦を巻いていた。その中心にいるにもかかわらず、ふわふわと絶妙な距離感をとって、彼はいつでも微笑んでいた。
大学時代のわたしは彼の独特な雰囲気に強烈に惹かれていたのだけれど、結局何もできなかった。目を見るとガチガチに緊張して、うまく話せなかったのだ。けれど今日は、自然と冗談を言い合っている。樹さんの雰囲気が変わったからなのか、私に本命が……壮亮さんがいるからかは、ちょっとわからないけれど。
会話が盛り上がり、二軒目でも軽く飲んだ。
「2軒目はわたしが払いますよ」
「今日はいいよ、無職でも金は持ってるから。そのかわり今度会う時おごってよ」
どうやらわたしたちには“次”があるようだ。
「櫻子ちゃん、終電何時?」
「もうすぐです」
「なんならうち泊まってってもいいけど」
「あ、大丈夫です」
そんな会話をして別れた。
それから樹さんとわたしは、ちょいちょい会うようになった。食事をしたり、美術館に行ってみたりと本当に健全なデートだった。壮亮さんとはできないデートだ。
一方で、壮亮さんとはこれまで通り。週に1度は食事をして、そのあとはホテルかわたしの家。彼が泊まっていくことはない。ひとりでベッドに取り残されると、彼との時間が現実味を失って、全部夢になる気がして怖かった。
ことが終わると、わたしはわざと彼に背を向けて目を閉じる。眠ったフリをするわたしの体に、彼がうしろから腕を回す。彼が身を起こすまでの短い時間は、もっとも切なく、もっとも苦しく、同時にもっとも幸せな瞬間でもあった。
壮亮さんが起き上がろうとする気配を感じて、わたしは彼の手をぎゅっと掴んだ。
「どうしたの?」
行かないでほしい。そう言いたかった。でもそれを口にしてしまったら、この恋が本当に陳腐な不倫になってしまう気がした。行かないで、奥さんと別れて、もっとわたしに時間を割いて。ありふれた、よくある不倫だと本当はわかっているからこそ、そういうセリフを吐きたくなかった。
「壮亮さん」
「ん?」
壮亮さんの声はやさしい。わたしを抱く手に力がこもり、頭のうしろに彼の息づかいを感じた。胸が苦しい。わたしはなるべく感情を抑えて告げた
「わたし、ほかの男の人と会ってるよ」
彼の指先が小さく跳ねた。短くない沈黙があって、壮亮さんは一度わたしを抱きしめたあと、小さな声で「ごめんね」と言った。
彼が着替えを終えるまで、わたしは横になったまま身じろぎひとつしなかった。準備の整った彼がベッドに腰かけて、わたしの頭をやさしくなでる。
「俺に言う権利はないけど……少し、さみしいな」
さみしいのはわたしのほうなのに。壮亮さんは本当にずるい。
「愛してるよ。おやすみ」
ひとりになってから、わたしはやっと泣くことができた。何が悲しいのか、あるいは悔しいのか、自分でもうまく言葉にできない。やっぱりわたしは壮亮さんが好きだった。ほかの男の人には替えられない。樹さんと会うのももうやめたほうがいいのかもしれない。奥さんがいても、結婚は難しかったとしても、彼はわたしの恋人だから。
泣きつかれて寝たのは朝方で、そこからやけにやさしい夢を見た。
夢の中で、壮亮さんは既婚者でも上司でもなく、単なるひとりの男性だった。わたしたちはなんのしがらみもなく、穏やかな日常を送っていた。
ーーー
月曜日に出社すると、数人の同僚の輪に手招きされた。
「ねぇ、知ってた? 観月さんの奥さん、もうすぐ臨月だって」
頭の中が真っ白になる。
「え? 何……」
「櫻子も知らなかったんだ。昨日わたし、観月さんが奥さんといるところに偶然会って。奥さんだいぶお腹大きくて、挨拶して少し話したら妊娠9カ月だって……」
生まれたらお祝いを送らなきゃ、みたいな話をされたと思う。うちの会社の慣例的には……直属の部下がお祝いを選んで……だとするとうちら?……付き合いが長いのは櫻子かな?
「櫻子、お子さんが生まれたらお祝い担当お願いしていい?」
見まちがいじゃないのか。その人は奥さんじゃなくて、たとえば親族の女性だったんじゃないか。そういう考えが頭をぐるぐる回っていた。わたしはほとんど反射で頷いた。すこし向こう、会議室から出てきた壮亮さんと目が合う。いつもどおりのやさしい笑顔。わたしは、わたしはちゃんと微笑み返せただろうか。
彼に奥さんがいるだけ、だと思っていた。すでに愛情の薄れた、男女としては終わった妻が。でも、そうじゃなかったかもしれない。少なくとも奥さんがいるだけじゃない。わたしの彼は、奥さんと、子どものいる人なのかもしれない。
(文・イラスト:白井瑶)