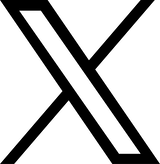東京で夢見たすべての人たちへ。シド・マオが15年間でたどり着いた場所
あこがれの人、がんばってる人、共感できる人。それと、ただ単純に好きだなって思える人。そんな誰かの決断が、自分の決断をあと押ししてくれることってある。マイナビウーマン読者と同世代の編集部が「いま話を聞いてみたい!」と思う人物に会って、その生き方(life)を切り取る(view)インタビュー連載【Lifeview(ライフビュー)】。
忘れもしない。2008年11月2日。
その日のわたしは、日本武道館の最上段にある立見席の柵に寄っかかり、愛しいロックスターの登場を心待ちにしていた。
チケット代は確か5000円ちょっと、地元から東京までの電車賃が往復4000円弱。今じゃポンと払えるような額も高校生だったわたしにとっては大金で、週4日ドラッグストアでバイトしながら必死に貯めた。それなのに。
やっとの思いで手に入れた初ライブの席は、ステージから一番遠い場所。背伸びしないとよく見えなくて、意気消沈したのを覚えている。足元にある段差に上がればかろうじてステージ全体が見えるものの、すぐさまスタッフの人に注意されてその作戦も撃沈。
憧れは、こんなにも遠い存在だったのか。もっと早く気づけよって話だけど、恥ずかしながら、あの日初めてそれを思い知った。
諦めの悪いわたしは、ステージの光景を脳裏に焼きつけながら、作戦の舵取りを大きく変更する。
「いつかこの客席とステージの距離、取っ払った場所に行こう」と。

彼が歌うことを選んだ理由
「本音を言うと、歌を選んだのは消去法。だって俺、ほかに取り柄がなくて。小学生のころの通知表は、ほとんどの教科が5段階中3か2の成績でしたからね。でも、音楽だけは違った。歌のテストのときだけはすごく褒められるし、カラオケに行くとまわりから『すげぇ!』って言ってもらえるし。『これだ! 見つけた!』と思った瞬間でした」
インタビューに対する書き手のスタンスが「大好き」という目線で始まるタブー記事は、世の中を探してもこの1本くらいしか出てこないと思うので告白しておく。
目の前で話すのはシドのヴォーカル、マオ。わたしは、この人を目指して編集者になった。
夢を持った経緯は別の記事で思う存分語ったので割愛するとして、わたしがこの「大好き」を伝える手段に文章を選んだのも同じく消去法。ほかに取り柄や、褒めてもらえることなんてなかったのだ、文章を書くこと以外。

「俺がなぜヴィジュアル系を選んだか、ですか? 最初は男が化粧していることには苦手意識がありました。それまで聴いていたのは、普通のパンクバンドだったし。
でも、ヴィジュアル系が一大ブームになって、そのときに聴いた曲やヴォーカリストの方たちがあまりにもカッコよすぎたんです。特に、黒夢、L’Arc~en~Ciel、GLAY。このバンドの音楽を聴いた瞬間は、本当に衝撃的だった」
そう語るマオさんの目は、彼がよく言う“わんぱくキッズ”そのもの。マオさんが話す、好きも夢も愛も。そこには莫大な情熱と野心がこもっていて、多くの人を熱狂させる。
だからわたしは編集者になって、もっと大勢に彼の話を届けたいと思ったのだ。どうしても。
東京と、夢がしぼんでいくあの感覚

シドの楽曲に『Dear Tokyo』という歌がある。
ド田舎で生まれ育ったくせに、東京で編集者になりたいというちぐはぐな夢を持ったわたしが、毎晩ベッドの中で聴き続けたそれだ。
「 21歳のとき『バンドで絶対売れなきゃ』と思って上京したものの、東京に着いた瞬間は仕事も家もなかったんです。地元で貯めたお金だけを握りしめて、それ以外何も持ってなかった。とりあえず初日は、『いいとも!のあれ見たいね』って、意味もなくアルタ前に行ってみたり。仲間と『うわ、いつもこの辺から引きで撮ってるよね』とか盛り上がってた(笑)」
当時を振り返るマオさんは、さらに饒舌に笑う。
「東京に来てから、“よくあるバンドマンの貧乏話”はひと通り経験したと思いますよ。ツアー中、お金がなくて宿を借りられないから、真冬の公園で髪を洗ったり。ほら、俺はヴィジュアル系なんで綺麗な姿でいないとダメじゃないですか」
破天荒すぎる上京ストーリーを、あまりにも飄々と楽しそうに話すもんだから「不安も恐れもなかったんですか……?」と、なぜかこちらが弱腰になる。だけど、さらっと返ってきたのは「売れる確信があったから」というまっすぐな目線と言葉。
「俺だけじゃない。あのころ、バンドでの成功を夢見て上京してきた全員がそうだったと思います。言っちゃえば、普通じゃない。みんな、どこか麻痺してる感覚」

彼が書いた『Dear Tokyo』の歌詞には、期待とか自尊とかがめいっぱい詰まっていて、上京を夢見る当時のわたしを心底わくわくさせた。だけど、歌には対照的で印象的なワンフレーズも存在する。“染まれば楽になることを知った夜 目的も放り投げた”と。
心に残っていた歌詞について問えば、「あぁ、あれはね」と、今度はどこか懐かしむようなマオさんの目線が向けられた。
「東京で活動をしていく中で、どうしようもできないことがいっぱいあったんです。
バイトをやらないとご飯が食べられない、まあ飯が食えないことなんて別にいいけど、一番大事なライブに出るための機材も買えない、バンドのプロモーションもできない。そうなってくると、次第にバイトをいっぱい入れ始めるようになって、今度はバンドのほうがおろそかになる……。
当時のバンドはみんなそうやってがんばっていたと思うけど、俺自身がこんなジレンマにはまっていったときのことを書きました」
そこにあったのは、本気で夢と向き合った人だけが知っている“しぼんでいく感覚”。
「俺たちは武道館や何万人っていう規模の東京ドームを目指してここに来たはずなのに、ふと気づいたら『ライブハウスに100人集めるにはどうしたらいいか』を喫茶店で真剣に何時間も話し合ってるんですよ。『あれ、なんだこれ』『なんか違うぞ』って。
バンドじゃなくても、みんなあると思うんです。純粋に描いていた夢から仕方なく離れていって、『しょうがない、しょうがない』って思っているうちに、いつしか夢の外にいる瞬間」

「だけど、俺はそこへ行きつく前に気づけたからよかった。気づいたきっかけは、まさにシドの結成でした。それまで組んできたバンドではたくさん失敗もしたけど、シドだけは最後のバンドにしよう、と。このメンバーだったらいける、っていう確信もあった。だって、シドは暴れ馬だけを集めたバンドでしたから。
メンバーの明希もShinjiもゆうやも、それぞれのバンドで『そいつにしか目がいかないじゃん』って奴らで集まった。この4人で、もう一度夢を見ようと思えたんです」
一緒に転がり続けたファンの存在
その後のシドは、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いだった。
メジャーデビュー前から、大きな会場をどんどんいっぱいにして、ライブのチケットはもはや争奪戦。シングルを出すたび順位を上げていく。
その軌跡は、もちろん全部知っている。10年前のわたしは、ちっとも取れやしないチケットを前にバイトを増やしてファンクラブに入ることを決意したし、フラゲ日にCDを手にしてはそれがどれだけ売れているか、オリコンのランキングを毎日チェックしていたし(今思えば、誰目線なんだってくらいのお節介だけど)。
「シドにとっての機転は、いっぱいあります。シングルがオリコンTOP10に入ったとか、メジャーデビューできたとか、武道館でやれたとか。
でも、俺にとっての一番は、お客さんの声だった。それまでは『キャー!』とか『マオー!』だったものが、いつからか地響きみたいに『うおぉぉっ』って聞こえてくる瞬間があって。ステージに立っている俺にしか聞こえない、あの音」

順風満帆に進んでいたシドのバンド活動。でも、挫折がなかったわけじゃない。2015年、マオさんはブログでメニエール病と声帯ポリープに悩んだ壮絶な2年間を打ち明けた。タイトルは「大切なファンのみんなへ。」。
「病気のことをファンに公表した一番大きなきっかけは、信頼関係にそろそろ甘えてもいいかなという気持ちになれたことです。
ずっと俺って、『こう見られたい』とか、カッコつけたプライドを持っていたから。これが直接的な病気の原因ではないだろうけど、その荷を下ろすだけで何かがちょっと変わるんじゃないかと思って書きました。実際、書いたことでめちゃくちゃ楽になれたし、それで今がある。だから、本当に書いてよかったなって」
マオさんにとって、ファンとはどんな存在なのだろう。
「ほかのバンドと比べると、うちってファンがシドを抱えてくれている比重が大きめだと思うんです。アーティスト主導で『こういう曲作ります、ライブやります。見て、カッコいいでしょ?』ってスタンスのバンドもあるし、そういう魅せ方ももちろんアリだと思います。
だけど、うちが16年やってきてたどり着いた場所は、そうじゃないだけ。
シドはもっと泥臭くて、ファンもメンバーなんじゃないかってくらい近くにいて、言うなれば一緒に転がり続けてきた関係性なんです」
その言葉は、きっと嘘じゃない。だって、やっぱりわたしは知っている。ライブじゃファンに「会いたかった」って愛を込めて歌う彼も、「ファンの存在を忘れたら俺は終わる」と大真面目に語る彼も。
「俺が病気になったときもそう。ヴォーカルの声が出ないってなったら『終わったねぇ』って人は離れていくのが普通でしょ? でも、シドのファンは違う。バンドが何年も活動を空けていたって、また帰ってきてくれる。
病気のあと調子の悪い日が続いて、ライブで声が出ない日はファンの子たちが俺の代わりにずっと歌ってくれることもありました。しかも、終わったあと『今日はたくさん歌えて楽しかった』なんて感想をくれるんです。
そんなファンっているのかな、ほかに。俺が進んできた道は正しかったんだって、ファンのみんながいつも教えてくれる」

「音楽っていろんなジャンルがあるけど、ヴィジュアル系はシドを育ててくれた場所だから。何より誇れる先輩方の存在がある。だから、それをうちのバンドで途切らせることはしたくないなって思いますね。後輩たちにもシーンを途切らせてほしくない。まあ、俺らも現役だから、バトンを渡すつもりはまだまだないけど」
マオさんの話はやっぱりマオさんで、なんの遜色もなかった。紡ぐ言葉ひとつひとつが真摯で、真剣で、本気で、わたしの大好きなロックスターがそこにいた。
日武の立見席、目を凝らしながらシドを見ていたわんぱくキッズに「作戦は成功したよ」ってそっと耳打ちしたら、一体どんな顔をするだろう。
あの日のわたしは、1分1秒でも長く憧れの存在を目に焼きつけようと夢中だったから、「ちょっと冗談はやめて」なんて、意外と簡単にあしらわれるかもしれない。でも、あとから事の重大さに気づいて、大慌てしたりして。
そんなことを考える取材の帰り道。「最高な人生だね」と、負けず嫌いな少女の耳打ちが、わたしだけにこっそり聞こえた。
(取材・文:井田愛莉寿/マイナビウーマン編集部、撮影:須田卓馬)
シド ニューアルバム『承認欲求』

2017年9月にリリースされた『NOMAD』以来となるシド待望のニューアルバム『承認欲求』。SNS全盛の昨今、まさに時代を象徴するワード<承認欲求>を表題曲とし、全曲新曲を収録。バンド結成15周年を乗り越えたシドの新章をとても斬新に、そして意味深く描いた世界観溢れる10曲がここに。
※この記事は2019年09月04日に公開されたものです