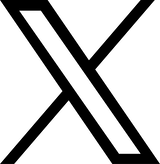東京タワーを見下ろす上空1万m #東京と働く。
「東京してる」って実感にどきどきするのは、私が東京の一部になれてないからなのかもしれない。深夜2時のモントークも、銀座駅から見上げる地上も、六本木ヒルズで観るくだらない映画も。ぜんぶ、ぜんぶ、ここで生きる誰かの大事な「トーキョー」。東京で働く女たちのストーリーを集めた、東京オムニバス連載。
どうも、大学進学とともに田舎から東京に放流された北海シャケ子です。

シャケ子の地元は午後6時の時点で、すでに真夜中くらいの錯覚に陥る。なぜなら、日の沈みが早く、お店も壊滅的にないので、あたり一面真っ暗になるから。しかも外には、人っ子ひとりいない。家から一番近いコンビニですら、歩いて10分かかる脅威のド田舎っぷり。おまけに夜12時には閉店する。もしかすると、ここは発展途上国なのかもしれない。夜、友だちと遊ぼうにも、よくあるチェーン店の居酒屋に寂れたカラオケだけ。カフェなんてない。そう、この街にはすずめの涙ほどのコンテンツ力しかない。
家では、母親が執事のようにせっせと世話を焼いてくれる。黙っていても次から次へと勝手に出てくるごはん、遊びに行くときは、必ず車で送り迎え。ここだけ見ると、まるでぬるま湯につかるような生活だ。
だけど、感謝するのと同時に息苦しさも感じる。ここには自由も選択肢もない。
おかげさまで、東京に帰る日は解放感しかない。帰り日の飛行機は、決まって夜。そして窓際の席は譲れない。新千歳空港の搭乗手続きで、血眼になって窓際の空席を探しているでかい女がいたら、それはシャケ子だと思っていい。
だが、離陸は眼中にない。外を見ても畑・山・畑・山・たまに民家のエンドレスだから。シートベルトサインが消えるころにはすでに爆睡している。大事なのは着陸。シートベルトサインがつくころ、ハッと目を覚まして、いい歳をした大人が今か今かと窓の外を凝視する。隣の子どももドン引きだ。

話を戻して、離陸とは打って変わり、眼下には光の海が広がっている。遠くには東京のシンボル・東京タワーがお出迎え。実際は足を踏み入れたことなんてないし、何の思い入れもないけど、「帰ってきた」とほっとする自分がいる。
ここには、自分を守ってくれる母親はいない。すべて自分ひとりの責任だ。たまに不安で押しつぶされそうになるけど、その代わり自由がある。死にそうになりながら働いて手にしたなけなしのお金で家賃を払い、真夜中に洒落たカフェで女友だちとお茶して、UberEATSでサラダを頼む。なんてことないことかもしれないけど、これが私の生きている証だ。
(北海シャケ子)
※この記事は2018年03月09日に公開されたものです