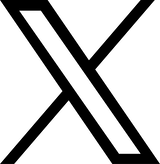自分のことが嫌いだった少女が俳優になるまで。内田慈が明かす「人生の原動力」
あこがれの人、がんばってる人、共感できる人。それと、ただ単純に好きだなって思える人。そんな誰かの決断が、自分の決断をあと押ししてくれることってある。20~30代のマイナビウーマン読者と同世代の編集部・ライターが「今話を聞いてみたい!」と思う人物に会って、その人の生き方を切り取るインタビュー連載。
取材・文:渡邊玲子
撮影:洞澤佐智子
編集:杉田穂南/マイナビウーマン編集部
現在公開中の映画『お母さんが一緒』で、江口のりこさん、古川琴音さんと三姉妹を演じている内田慈さん。実は、内田さん自身も「3つ違いの三姉妹」という共通点がある。
「慈」と書いて「ちか」と読む。芸名なのかと思いきや実は本名で、「厳格な教育指導をする父がつけてくれたこの名前から解放されたい」との思いから、なんと芸名を「内田地下」にしようと考えていた時期もあったのだそう(周りに大反対され、ギリギリのところで思いとどまったとか……)。
家を飛び出し始めた“家賃2万5000円の4畳半風呂無しアパート”生活
「私は三姉妹の末っ子で。三姉妹みんな漢字一文字で、音(読み)は二文字なんですよ。末っ子ゆえ、特にあれこれ試行錯誤の上でつけてくれたようなんですが、文字通り『慈悲深い』とか『慈しむ』といった意味合いが込められていて。ことあるごとに父から『名前負けしないようにね』って言われていたので、私の中ではプレッシャーでしかなくて……。自分のことが嫌いだったので、演劇を始める時に名前を変えたいと思っていたんです」
そう話す内田さんは、舞台を始め、数々の映画やドラマで活躍されていて、自分の好きな道を邁進しているように映る。でもじっくり話を伺ってみると、抑圧された環境から家出同然で抜け出し、20代半ばごろまでは、「阿佐ヶ谷の家賃2万5000円の4畳半風呂無しアパートを拠点に、バイトで食いつなぎながら小劇場の舞台に立つ日々を送っていた」というから驚かされる。
「父は塾講師をしていたこともあって、教育に関してはとにかく厳格だったんです。だから私は何をやるにしても『どうせダメって言われるんだろうな』って、端から諦めがちでした。しかも、『ここは空気を読んでこうしとくか』みたいに、三女だからバランスを見てしまうところもあって。常に自分の感情を押し殺して生きている感覚がありました。でも、学生時代に演劇と出会って、初めて、ありのままの自分を認めてもらえた気がしたんです。『本当はもっとめちゃくちゃやってもいいんだよ』『別に変でもいいんだよ』って」
阿佐ヶ谷時代は、まさしく「若い頃の苦労は買ってでもしろ」を地で行くような感覚で、「『いつかインタビューのネタにできるかも……!?』というくらい前向きに過ごしていた」という内田さんだが、「とはいえさすがにキツいと思う日もありました(笑)」と振り返る。
「風呂無しどころか、洗濯機すら持ってなかったので(笑)。真冬に水しか出ないアパートのシンクで頭を洗ったり、溜め込んだ洗濯物を抱えて近所のコインランドリーまで何度も往復したりするのは、実際にやってみると『こんなにシンドイものなんだ!』って痛感させられたのも事実(苦笑)。ですが、『他の人があまり経験したことがないことを、いま私はやっているんだ!』という風に思えた、という意味では、どこか、自己肯定感のアップにもつながっていたというか。自分自身の新たな一面の発見になっていた気もします」
なかなか思うようにいかないフリー時代
19歳で芝居を始めた当時は、役者をやるなら劇団や事務所に所属するのが一般的であることさえ知らず、チラシに印刷されていたオーディションの告知を見ては、芝居のジャンルや公演規模を問わず興味の赴くままに受け、フリーで活動していたという。芝居はあくまで自分が好きだからやっていることであり、「仕事と思ってなかったからこそ頑張れた」のだとか。
25歳ごろから舞台だけでなく映像の仕事も始めたことで、自身でスケジュール管理をするのが難しくなり、事務所に所属。以降も、活動基盤を舞台に置きつつ、守備範囲も広げていった。だが、仕事環境にも慣れ、大抵のことは経験値で対応できるようになった世のアラサー女性が直面するのと同様、内田さんにも少しずつ心境の変化が生じ始めたという。
「ちょうど30代半ばの頃に、『大きな冒険をするなら、今が最後のチャンスなのかもしれない』って、直感的に思ったんです。自分としてはまったく手を抜いているつもりはなくても、芝居を始めた時の衝動や情熱みたいなものが、だんだん持てなくなってきて……。どこか、こなしている感覚になっていたのかもしれません。他にもいろんなことが重なり、そのタイミングで長年所属していた事務所から離れる決断をし、マネージャーと2人体制での新たなスタートを切ったんです」
だがそれからほどなくしてコロナ禍に突入。急に先行きが見えなくなったこともあり、「お互いもう一度見つめ直そう」と、マネージャーとそれぞれ別の道を進むことを決意。2年近く完全フリーランスとして活動していたものの、またしてもスケジュール管理の壁にぶつかって不安に感じていた時に、舞台『ガラスの仮面』で共演して以来、親交のあった貫地谷しほりさんから現事務所を紹介され、再び事務所に所属することにしたのだそう。
めんどくさい自分にとって芝居は「必要不可欠な心のリハビリ」
慣れ親しんだ場所から離れ、予期せぬコロナ禍で完全フリーの大変さも身を持って知ったからこそ、自分にとってベストと思える環境と巡り合えた内田さんが、目指す未来とは?
「4月クールのドラマ『Re:リベンジ-欲望の果てに-』で演じた岡田先生のように、キビキビ行動する役を振っていただくことも多いのですが、こう見えて私は、とてものんびりした人間なんですよ。役者の仕事の醍醐味って、自分が演じる役の人生を通して、分かり合えない他者とどう向き合い、いかに生きていくべきか……といった哲学的なテーマに、じっくり思いを巡らせることができることにあると私は思ってて。ゆっくりじっくりひとつのことに向き合える点が性に合っているなと思います」
「年齢や経験を重ねるにつれ、『こういう時はこう対処すればラクなんだな』とか『こうすれば周りに迷惑をかけないんだな』ってだんだん分かるようになってきた部分もありますが、残念ながら私自身はまだまだめんどくさい自分のことを十分には飼い慣らせていません。きっと私は一生かけて自分自身となんとか折り合いをつけて生きていくんだと思います。役を演じる上でそれが活かせるのも、この仕事ならではですよね」
1対1で真正面から向き合うインタビューというのは、どこかカウンセリングに近い部分もあって、普段自分では気づいていなかった“本当の私”に、ふとした瞬間向き合うことになったりもする。実際にこの日も、「いま、取材を受けながら自分でも初めて気づいたんですけど……」とちょっぴり戸惑いながら、内田さんは複雑な胸の内を明かしてくれた。
「育った家庭環境によって抑圧されていなければ、きっとここまで自分のことをめんどくさいとは思わずに済んだかもしれないですが(苦笑)、もしもあの頃の私が自分のことをそれほど嫌いじゃなくて、もっと自分に自信があったとしたら、『芝居をしたい』とか『俳優になろう』なんて、思わなかったような気もするんですよね。だから、ひょっとすると全ての物事は、“表裏一体”とも言えるのかもしれないですね」
「不思議なことに、お芝居をしている瞬間だけは自意識から解放されるんですが、舞台挨拶や何かで人前に立つ際は、無駄な自意識が邪魔をしていまだに緊張してしまうんです。それこそ、コロナ禍の緊急事態には『不要不急』という言葉が叫ばれましたけど、お芝居をすることは私にとっては決して不要不急ではなくて。ある意味必要不可欠な心のリハビリのようなもの。その切実さから生まれた表現が結果、観ている方たちにとっても切実に心動かすものであれば良いなと思っています」
内田さんが言うように、自分のことを「めんどくさい」と思う瞬間は、日常生活を送っている中で私自身にもある。たとえば、SNSで何かを発信しようにも、「これを書いたらどう思われるだろうか……」と、躊躇してしまうこともたびたびだ。でも、内田さんが「自意識を忘れられる」芝居と出会い、めんどくさい自分と上手く付き合うためのリハビリを続けているように、私たちにも「自分で自分を認めてあげられる瞬間」が訪れると信じたい。
そして「自分自身が何かに没頭するだけでなく、自分の推しが出ている作品を観たり聴いたりしている瞬間こそ、自己肯定感が得られているのかもしれない」と思ったりもする。
ちなみに、内田さんいわく、「かつて、私が芝居をすることにあれだけ大反対していた両親も、今となっては手放しで応援してくれています。おかげさまで、父との関係も良好です(笑)」とのことなので、ご安心を。人間、何が自身を突き動かす原動力になるかなんて分からない。「表裏一体かもしれない」ことも自覚しながら心のリハビリに勤しみたい。
『ありきたりな言葉じゃなくて』
青春から遠くも近くもない32歳の藤田拓也は、町中華を営む頑固な父と愛想のいい母と実家暮らし。ワイドショーの構成作家として毎日徹夜でナレーション原稿を書き散らす日々が続いている。
そんな時、先輩の売れっ子脚本家の推薦によって、ようやく念願の脚本家デビューが決まった。「脚本家」の肩書を手に入れ浮かれた気持ちでいる拓也の前に現れたのが、鈴木りえだった……。
脚本家の青年と、どこにでもいる普通の“彼女”が出会い――。
2024年12月20日(金)より全国公開
©2024テレビ朝日映像
※この記事は2024年08月21日に公開されたものです