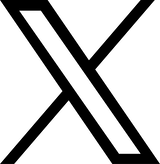彼が死ぬまでやろうって決めたこと。山田裕貴インタビュー
なんて言うんだっけ、こういうの。あ、そっか役者魂だ。
こんな表現を思い出したのは、目の前にいる彼のせい。役者って仕事が存在しなかったら? 私の意地悪な質問に「生きてないっすね」なんて、まっすぐな気持ちをさらっと吐き出したから。なんだか嘘っぽい記事になる気がして、役者魂とか大げさな言葉を使うのはダサいと思ってたけど。このときだけはどうしても使いたくなった。

次やることは死ぬまでやろうって決めた。
「プロ野球選手だった父親にずっとコンプレックスがあったんです。野球少年だった自分は父にすごく壁を感じていて、負けちゃいけないって漠然と思ってた。父を意識していた分、全然楽しくやれていなかったんです。だから、野球を好きになれなくて結局途中でやめてしまいました」
山田裕貴の父親と言えば、元中日ドラゴンズ選手で現広島東洋カープコーチの山田和利で知られている。本気で打ち込んできた野球に対する思いは、大きすぎる父の背中を意識するあまりコンプレックスでいっぱいになっていた。そんななか、通っていた高校の野球部が甲子園に出場したことで彼の気持ちに変化が起きる。
「高校3年生のとき、僕が通っていた高校が甲子園に出たんです。応援に行った甲子園球場で試合に出る友だちの姿を見ていたら、ありえないくらい涙が溢れてきて。そこで思い出したんです。『俺は野球をやれとは言ってない。自分でやるって言ったことをなんでやめたんだ? だから悔しいんだぞ』っていう父親の言葉を。それで、また涙が止まんなくなった。当時の僕は、自分の人生に自分で蓋をして諦めちゃってたんです。野球を続けていたら、甲子園に行けていたかもしれないのに」
そして、少し間をおいて紡がれた彼の言葉に現場の時間が一瞬止まる。
「だから、次やることは死ぬまでやろうって決めました」

18歳の山田裕貴が死ぬまでやろうと決めたこと。それこそが役者だった。野球の次はなんで役者? そう疑問に思う人も少なくないと思う。でも、話を聞いてみると答えはちゃんと彼の中にあった。
「小、中、高といじられキャラだったんですよね。『モノマネやれ』『一発ギャグやれ』って、人前で何かをやらされることが多かった。家だと父が王様だからめっちゃ静かにしてた分、みんなが笑ってくれる感覚が素直にうれしかったんです。学校に行けば、友だちが『山ちゃん、おもしろいね』って言ってくれて『あ、俺おもしろいんだ』って気づいた。人前に出ることが楽しいと思えた瞬間でした」
もちろん、父親や家族と過ごしてきた時間にだって役者としてのルーツはある。
「父親や家族との思い出と言えば、テレビや映画を一緒に見ることでした。そこで『じゃあ、俺はここに出る人になろう』って思ったのがはじまり。そのときは、テレビに出る回数なら親父を越えられるんじゃないかって根拠のない自信を持っていたんです。僕の役者人生はそこから。この道を目指したいちばん大きなきっかけですね」

高校を卒業した彼は名古屋から上京し、芝居の勉強をするため養成所に入ることになった。ただし、そこに入ったからといって全員がデビューできるとは限らない。その厳しさは、当時を「首の皮一枚で繋がっているような状況だった」と振り返るほど。役者になれる保証なんてない。芝居の世界で生きていく決断に迷いはなかったのか。
「もうないんすよ。僕にはお芝居以外にやれることが。『HUNTER×HUNTER』のワンシーンじゃないけど、同じように『もうこれで終わってもいい』と思えるほどの決意だった。『俺にはこれしかない』ってくらい死ぬ気になると、人間は目の前のことしか考えられなくなるんです。だからこそ、迷いなくお芝居にはのめり込めたし、熱くなった。悔しさだって覚えた。はじめてちゃんと心動いたのがこのお仕事でした」
帰り道、父と母が見送ってくれた、
18のときに見送ってもらったときは不安しかなくて
本当に生きていけるのか
わからなかった。
覚悟を決めた。
でも、27になって
ちょっとは戦えるようになって
今見送ってくれた
父と母の表情は
「お前なら出来る」という顔をしてくれていた気がする。ありがとう pic.twitter.com/O1NiNNWySj— 山田裕貴 (@00_yuki_Y) 2017年12月6日
これしかないからこそ、決意は十分だった。でも、弱い気持ちがまったくなかったわけではない。群馬の田舎から上京した私は、先日の彼のツイートがずっと心に残っていた。1万件以上の「いいね」が集まったのは、きっと多くの人を突き動かす何かがあったから。名古屋から上京したときの気持ちをこんな風に語ってくれた。
「名古屋を出ることになったあの日、母親と妹が心底不安そうに僕を見送っていたのを感じたんです。無理して笑ってくれてるのが痛いほど伝わってきた。自分だって悲しく見せないようにしてたけど、家を出る瞬間はめちゃくちゃ不安でした」
地元の名古屋に帰るべきか、心から悩んだ時期だってある。
「上京して2年後の20歳のとき、養成所から事務所に入るためのオーディションに落ちたんです。それで『名古屋に帰らなきゃいけないかもしれない』って母親に電話したこともあった。でも、このツイートのタイミングで帰ったときは、家族に『次これやるよ』『あれに出るよ』と報告できる自分になれていたんです」
いい芝居を見ても、悔しいって思わなくなった。

役者という仕事に対してここまで熱い気持ちを持っている彼は、さまざまな人の芝居を見て吸収することを怠らなかったはずだ。刺激を受けているライバルは? そう尋ねると「お芝居をされている方全員」という答えが返ってきた。
「テレビや映画などのメディアに出ている方以外にも、素敵な役者さんはもっとたくさんいます。それぞれにやり方や進みたい道があるからこそ、メディアに出ない人もいるだけなんです。フィールドはちがっても、尊敬する役者さんたちは数え切れないほどいますね。そういう人たちみんなに『あいつは役者だ』と言ってもらえる存在にならないとなって」
私の場合、素敵だなって思う記事にめぐりあったときは大抵最後まで読めない。だって読み進めれば進めるほど「私にはこんな記事作れない」と感じて、悔しさでいっぱいになるから。山田裕貴は、心を揺さぶられる他人の芝居を見て悔しいと思わないのか。
「今は悔しいというよりも、さっき言ったように素敵だなって気持ちが先行する。昔はくそ負けず嫌いだったから、やっぱり悔しいって気持ちがすごかった。それは他人の演技が見られないほどで。でも、今は『ここがいいから、世間もいいって言うんだろうな』って視点で見ているし、吸収すべきものとして考えられるようになりました」
悔しいという感情の先に、そんな景色があるなんて言われなければ気づかなかった。彼がそう考えられるようになったのは、きっと山田裕貴という役者のレイヤーがひとつ上がったからなんじゃないかと思う。
「悔しいっていう感情から抜け出すまでは時間がかかりましたよ。気持ちに変化があったのは24、25歳じゃないですかね。今売れてるって言いたいわけじゃないけれど、作品にまったく出られない時期はやっぱり卑屈になっちゃって。『なんで、なんで、なんで!』って悔しい思いをたくさんしました。でも、そういう期間に痛みを味わっていて逆によかったなって思うんです。だって辛い感情を知っている分、人の気持ちをわかろうとするようになれたから。役だってそう。僕が演じるのは、ひとりの人間なんです。役の気持ちをわかろうとする姿勢が、僕のお芝居に生きてくる」

山田裕貴という人間から役者という居場所を奪ったら、どうなるんだろうか。答えはもうなんとなく予想がついていた。でも、最後は彼の口から聞きたかった。ここで、冒頭のシーンになるわけだ。――もし、役者という仕事がこの世に存在しなかったら。
「生きてないっすね。この仕事以外だったら自分らしく生きてないと思う」
なくなったら生きていけないものってなんだろう。私にはすぐにそれが見つからなかった。ずっとなりたくてやっと掴んだ編集者の仕事だけど、なくなったからって死ぬわけじゃない。それくらい、彼がさらっと言ってのけた言葉を自分の言葉にするのは難しかった。それでもこの記事は死ぬ気で書こうと思った。彼の言う「なくなったら生きていけないもの」が見つかるような気がしたから。
「これで役者をやめて、のうのうと生きてたらすいません」
そう言っておどけた彼だけど。逸らしたくなるほどに意志の強い眼差しと、嘘がつけないまっすぐな表情を見て私はちょっと可笑しくなった。
またまた、やめる気なんて絶対ないくせに。
(取材・文:井田愛莉寿/マイナビウーマン編集部、撮影:前田立)
※この記事は2017年12月20日に公開されたものです