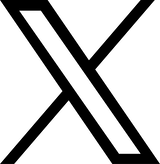「ズルい自分」に立ち向かいたい人へ。『それでも女をやっていく』書評
仕事、結婚、からだのこと、趣味、お金……アラサーの女性には悩みがつきもの。人生の岐路に立つ今、全部をひとりじゃ決め切れない。誰かアドバイスをちょうだい! そんな時にそっと寄り添ってくれる「人生の参考書」を紹介。今回は、実体験をもとに女を取り巻くラベルを見つめ直すエッセイ『それでも女をやっていく』(ひらりさ・著/ワニブックス刊)を、コラムニストのジェラシーくるみさんが書評します。
ちょっと重たくて、面白いエッセイを読んだ。
『それでも女をやっていく』
そのタイトルを見たときに「人は女に生まれるのではない。女になるのだ」というフランスの哲学者・ボーヴォワールの言葉を思い出した。
「女になった」瞬間
私が小学生高学年の頃、祖母の家でそれはやってきた。今まで感じたことのない痛み。お腹を内側からジリジリ焼かれているような不快感の後、拳で腰を殴られたような鈍い痛みを感じた。
祖母が炊いてくれた赤飯を「これが噂に聞くやつか……」と不思議な気分で食べたのを覚えている。
夜、迎えに来てくれた父の車に乗り込もうとして、いつものようにガードレールをまたいだ私を祖母は穏やかにいさめた。
「XXちゃん、もうそんなことしたらダメ、今日から女になったんだから」
祖母のぽかぽかした呆れ顔とは対照的に、私がそのとき感じた居心地の悪さ、父に聞こえていないかというざらついた恥ずかしさの感触は、今も胸の内に刻まれている。
自分が「女」だと感じさせられるのは、このような綺麗でわかりやすい瞬間だけではない。
本著では、「女」にまつわる葛藤や困難、不自由さ、味わい深さ、そして「娘」「腐女子」「異性愛(ヘテロ)」「弱者・被害者」など、著者が自ら付し、また他人から付せられてきた様々なラベルについての考察が綴られている。
起きた事象や過去の感情から少し距離を置き、どこか俯瞰しながら書かれたノンフィクション本が世にはたくさんある。テンポ良く、小気味よいエッセイも。
だが本書は、そんな余裕を許さない。
自身の物語をつぶさにルーペで観察し、拡大された断片を読者にずいっと差し出してくる。ときにユーモラスで、ときに自虐的で、ときに手厳しい。
ええ、ここまで曝け出していいの? とこちらが赤面しながら両手で顔を覆い、人差し指と中指の間からおずおず覗き見してしまうような、そんな生々しいシーンも多々ある。
テーマとしては、母と娘、女友達、「男」側からのジャッジ、妊娠出産、女性性にまつわるコンプレックス、性愛のかたち……など実に色とりどりだが、読み進めていくと、著者のあけっぴろげな独白と真摯で鋭い分析に、たちまち身包みを剥がされる。彼女の自意識と私のそれが共鳴し、自分の中の劣等感、ずるさ、甘さをすべて暴かれている感覚に陥る。
ついた傷は、ごまかせない
サークルや会社などのコミュニティに入ったとき、よく同期の女を並べて誰派かを大声で話す男どもがいる。誰が「アリ」で誰が「ナシ」かを意気揚々と酒のネタにする男どもがいる。
何度その場に立ち会っても、私は聞こえないフリをしたし、直接その話題をぶつけられたときも、あくまでも柔和な態度を保ち、必死にへらへら拒絶していた。
その数年後、居酒屋にて、同期の女友達と「誰が一番男根が大きそうか」のテーマで30分かけて議論をし、太さと硬さの2軸で男たちのランク付けをしてやった。そのゲスな30分は仕返しだった。圧倒的に正しくないかたちで、この上なく下品なかたちで、敵に泥を塗り返した。
本来ならその場で「そういう下世話な話はここでしないでください」とほぼ初対面の男たちに冷や水をぶっかけてやればよかったのだ。だが、それができる女がこの世にどれほどいるだろうか。
臆病でずるい私は、その場ではやり過ごすことしかできなかった。
男性から容姿でジャッジされ、愛嬌や媚びを強いられ、性的な眼差しを無遠慮にぶつけられ、機能や記号のように消費され、ときに物のように扱われた経験は、女性なら誰しもが通ってきた道だろう。こんな風に断言できてしまうのは胸糞悪いが、この国の社会で数十年生きていれば、当たり前のように小さな傷が刷り込まれる。
だが、その場で唾を塗って誤魔化したはずの傷は、実はまだそこに残っているのだ。砂やゴミで傷ついた車のフロントガラスが、光によって乱反射するように。
この本は、太陽光であり、対向車のライトだ。ときにやわらかく、鋭く傷を浮かび上がらせ、私たちは自分の心身についた無数の傷を再認識する。
「下ネタで笑う空気も嫌だったが、そこに多分にあった、男だけの内輪感、その内輪を盛り上げる装置として使われている外野としての自分、という状況が嫌だった。深夜終電で降り立った地元駅でドロドロの吐瀉物をうっかり踏んでしまったときの気分だった。
吐いた奴が悪いのだが、回避できずにこんな目にあっている自分という存在が悪い、という気がしてくるあれ。そんな世界への行き場がない怒りに支配された」
(本文より引用)
私は吐瀉物を踏んでも、かけられても、多分へらへらしてきた側の人間だ。それどころか、昔の自分は隣の女性がかけられたのを見て見ぬフリをして、自分にかからないようスッとその場を立ち去ったこともある。
「女をやっていく」とは
これは私が共感した一例ではあるが、本書には「女」の人間関係の難しさや、「女」の連帯に関するエピソードも多く載っている。
相手との適切な距離感を測り損ね、「友達ならわかってくれるよね」の甘えから始まったすれ違いの話だったり、奇妙な縁で引き合わされた女性と築く新しい友情の話だったり。
最後の3章目で、著者はジェンダー論・メディア論をイギリスで学び直した話の後に“フェミニスト”という言葉の持つ熱と危うさについて言及している。
私も自分なりのフェミニズムを盾に意見や要求を正当化し、特定の「男」または「男」全般に対して「加害者」のレッテルを無意識に貼ってしまうことがあると自覚しており、声高々に“フェミニスト”を名乗ることはできない。
それどころか、フェミニズムやジェンダーについて学び、本を読み重ねるほどに、“フェミニスト”という言葉を聞くと心臓の毛がざわっと逆立つのだ。
本書は、一つの問いで締めくくられている。
「あなたは、フェミニストですか?」
私たちの、こじれにこじれた自意識がほどけるときはくるのだろうか。
傷つけられ、誰かを傷つけ、やり過ごし、やり過ごしたことをふいに後悔し、過去の自分への問いかけを繰り返すことで少しずつ知恵もついて面の皮も厚くなり、社会や「ズルい自分」と闘えるようになってくる。
その過程が「女をやっていく」ということなんだろう。
(ジェラシーくるみ)
※この記事は2023年06月25日に公開されたものです