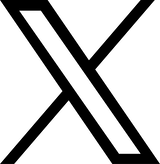【街の色、街の音】第1話:各駅停車日和

渋谷駅のホームで、右側に止まっていた急行ではなく、各駅停車に乗りこんだ。 実家がある久我山までは、もちろん急行のほうが早く着けるとわかっている。しかもこちらのほうが発車時刻も遅い。
座席に腰かけ、膝の上にバッグと紙袋を置く。紙袋の中には、さっき買ったばかりの豆菓子詰め合わせが入っている。母親の好物だ。菓子類をさほど好まない父親も、ここのものなら喜んで食べるので、帰るときには渋谷で買っていくのが定番となりつつある。
実家に帰るのは、たいてい水曜日。勤務先の不動産店は水曜が定休日で、確実に休みだとあらかじめわかっているから、調整しやすいのだ。
時刻は予定していたよりもだいぶ遅くなった。渋谷でついいろんなお店に立ち寄ってしまったからだ。豆菓子を買えば用事は済んだのに、ふらふらと歩き回り、途中でカフェにまで入ってしまった。母親には、遅いと文句を言われてしまうかもしれない。
それでもあえて各停に乗りたい気分だったから、悩まなかった。
急行電車が先に発車する。背中を向けるような位置で座っているので、姿は見えないけど、駅員さんのアナウンスのあとに、走り去っていく音がした。
車両内はすいているというほどではないけど、いくつか空席もある程度の混み具合だ。窓からの光が心地いい。快適、と思いながら、わたしは背中を座席にあずけ、目を閉じてみる。
このあいだ実家に戻ったのはいつだっただろう、と考えてみて、車窓からあじさいを見たのを思い出す。青や紫やピンクが、車内からでもとても美しく見えた。写真を撮っている人もいた。あのときもやっぱり各停に乗っていたのだ。あじさいが咲いていたのだから、五月の末か六月あたり。三ヶ月以上が経つのか。
ということはまだ恋人と別れていなかったときだな、と気づいて苦しくなる。さすがに別れから一ヶ月以上が経ち、泣き出すようなことはなくなったけど、胸がしめつけられる感覚はいまだに抜けない。抜けることなんてあるんだろうかと不安になってしまう。
アナウンスが流れ、電車が滑るように動き出す。少しして目を開けると、空席だったはずの向かいの座席に、女子高生らしき制服姿の二人が腰かけていた。平日の午後だから、ちょうど帰宅時間なのか。でも他に学生らしき子は見当たらないから、たまたまかもしれない。わたしの視線なんて気にも留めず、二人が話し出す。
「ねえ、やっぱり、告白とか無理かも」
「なに言ってるの。余裕でいけるってー」
そう大きくはないけど、二人とも通る声だ。どうやら一人がこれから好きな人に告白するらしい。不安がるその子を、もう一人が、あらゆる言葉で慰めたり元気づけたりしている。しばらく続いたやりとりの中で、励ます側の子が言った。
「大丈夫って思ってたら、絶対大丈夫だよ」
そこだけが妙にゆっくりと、そしてハッキリと耳に届いた。大丈夫。まるで、わたしに向けられた言葉のように。
いつまでも続きそうな彼女たちのやりとりに、かつて自分も、女子高生として井の頭線に乗っていたことを思い出す。もう十年ほど前だ。彼女たちのように、たいていは、一番仲の良かったさゆりと二人で行動していた。そういえば、さゆりとはしばらく連絡を取っていないけど、元気にしているだろうか。
大丈夫。大丈夫。紙袋の重みを膝で確かめながら、声に出さずに繰り返す。いつのまにか、二十代も終盤にさしかかり、実家の両親におみやげを買うくらいには大人になった。時は流れる。
電車がゆるやかに止まる。各駅停車はゆっくりと、けれど着実に目的の駅へと近づいていく。こんなふうに少しずつでも、今の苦しさもいつか記憶に変わっていくのだろうと信じられる気がした。
この物語で登場した京王井の頭線沿線マップ

街の色、街の音:その他の物語はこちら
【第2話】カフェ日和
視線を感じ、ふと顔をあげると、嶋本さんがこちらをじっと…
【第3話】成長日和
海斗と手をつなごうとしたが、いいの、と…
【第4話】参拝日和
後輩たちに合コンしましょうよと誘われて…
【第5話】買物日和
ハートのつり革。二つ並んだそれに、引き寄せられ…
![]()
関連リンク

著者/加藤千恵
北海道旭川市出身の歌人・小説家。立教大学文学部日本文学科卒業。2001年、短歌集『ハッピーアイスクリーム』で高校生歌人として脚光を浴びる。短歌・小説・詩・エッセイなど幅広く活動中。
提供:京王電鉄株式会社