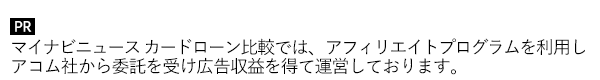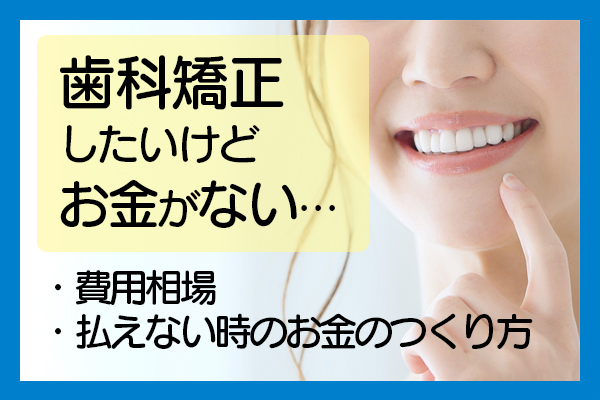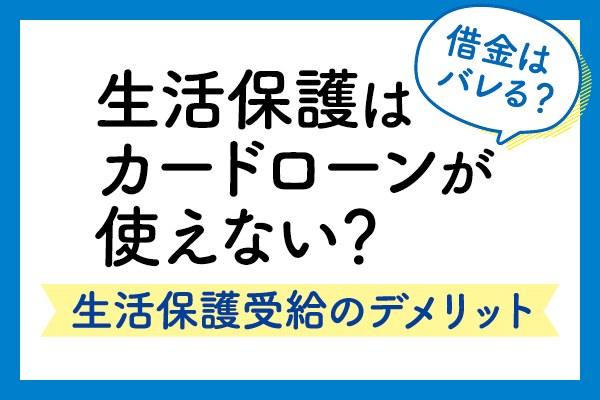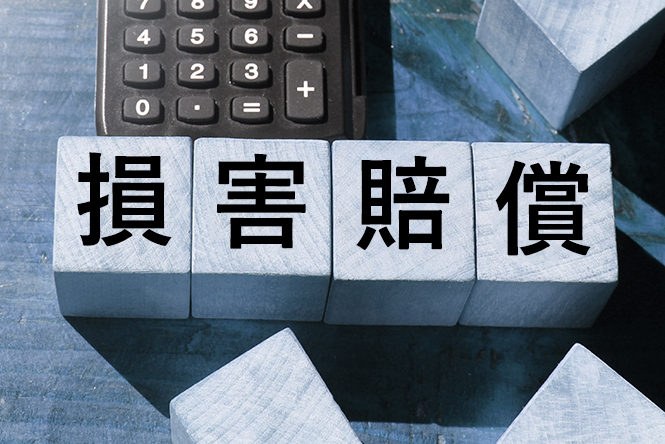国からもらえるお金、自治体から返ってくるお金一覧。もらわなきゃ損!

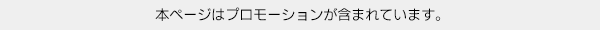
「マイホームが欲しい」「子どもの教育費がかさむ」「通院にお金がかかる」など、生活をするには何かとお金が必要ですよね。日々なんとなく支払っている費用のなかには、国や自治体からもらえる、または返ってくるお金が潜んでいるかもしれません。
実は自治体によって内容や名称が異なるため、あまり知られていない補助金もいろいろあるんです。
そのほかにも、住宅ローン減税では最大400万円の控除を受けられるなど、知っているだけで多額の節税ができる制度もたくさんあります。
適用する制度は使わないと損ですよね。ここでは住宅関連、子育て関連、医療関連、その他知っておくと、お得な制度をいろいろ紹介していきます。
プロミス
に今すぐ申し込む
この記事の目次
住宅ローン減税とすまい給付金の併用で賢く節税!リフォームにも適用
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」は消費税引き上げの負担を軽減するために、制度が大幅に拡充されました。
住宅ローン減税は新築だけでなく、中古住宅も対象でリフォームに適用できる場合もあります。お得な住宅ローン減税と併せて利用できる、すまい給付金についても紹介します。
住宅ローン減税(控除)制度は最大520万円の控除を受けられる!?
住宅ローン減税制度は住宅ローンを借りて、マイホームを取得する際の金利負担を軽減するための制度です。平成26年の消費税引き上げに対応するために制度拡充が行われました。
この制度では最大で520万円の控除を受けることができます。
控除されるのは以下の金額が少ない方の1%で、10年間所得税から控除を受けられます。
- 年末の住宅ローン残高
- 住宅の取得対価(すまい給付金の額は控除される)
新築だけでなく、中古住宅も対象となる住宅ローン減税は増築や省エネ、バリアフリー改修の費用が100万円を超える場合、その工事費用も減税対象となります。
なお2022年12月末までに入居をした場合に限り、消費税率の引き上げに伴い控除を受けられる期間が13年間に延びており、最大520万円の控除を受けることができました。
すまい給付金で住宅購入のときに最大30万円もらえる!?
上記で紹介した「住宅ローン減税」は、所得税などから税金を控除するので、収入が少ない人にとっては大きな効果が望めませんでした。そのため実施されたのが「すまい給付金」です。
すまい給付金は最大で30万円(消費税10%が適用される住居を取得し、令和3年12月までに入居した場合は最大50万円)をもらうことができ、住宅ローン減税と併用できます。
すまい給付金の対象者はこちらです。
- 住宅を取得して登記上の持分を保有し、その住宅に居住する
- 一定以下の収入※である
税金8%:目安として510万円以下
税金10%:目安として775万円以下
すまい給付金でいくら受け取れるかはこちらのサイトでシミュレーションできるので、参考にしてください。
出産から進学まで子育てに役立つ制度!年齢別のもらえるお金を紹介
妊娠・出産から就学にかかる費用など、子育てには何かとお金がかかりますよね。実は国や自治体が行う子育て支援のための給付金は、いろいろあるんですよ。
例えば出産の際には出産育児一時金や育児休業給付金、その後も中学生までは児童手当、高校に上がってからは高等学校等就学支援金や私立高等学校等授業料軽減助成金などの制度があります。せっかくなので使える制度は利用しましょう。
出産育児一時金は子ども1人につき42万円支給される給付金
出産育児一時金は出産費用や育児にかかる費用負担を軽減するために支給される給付金で、1人につき42万円が支給されます。在胎週数が22週未満など、産科医療補償制度加算対象出産でなければ40万4千円(平成27年1月1日以降)が支給されます。
受け取り条件は次の3つです。
- 健康保険の被保険者またはその被扶養者
- 妊娠4カ月以上で出産した人
- 産科医療補償制度加算対象出産でない人
児童手当は0才から15才まで受け取れる!最大15,000円支給
児童手当は0才から満15才(誕生日後の初めの3月31日まで)の児童を養育している人を対象に支給される手当金で、金額は年齢によって異なり月額5,000~15,000円が支給されます。※2
0才から満15才までの支給月額はこちらです。
| 年齢 | 月額 |
|---|---|
| 0~3才未満 | 15,000円 |
| 3才~小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 10,000円 |
所得制限の限度額を超えている世帯の場合でも、月額5,000円の児童手当を受け取ることができます。
3歳~小学校修了前までに支給される金額の「第3子以降」とは、高校卒業までの養育している子どもの内、3番目以降のことを指します。すでに大学生以降にまで子どもが成長しているのであれば、「第3子以降」には数えられません。
児童手当を受け取るには、国からもらえるお金としてお住いの市区町村に申請手続きを行う必要があります。里帰り出産などでお住いの市区町村以外で出生届を出した場合は、別途お住いの市区町村で申請手続きを行います。
新制度の高等学校等就学支援金で授業料負担を軽減!
この制度は高等学校等の授業料を支援するための制度です。市町村民税所得割額が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯に支給されます。所得によっては支援金が増えることもあります。
全日制の高等学校の場合は月々9,900円支給され、3年間の総支給額は356,400円です。
学校の種類別の月々支給される金額はこちらです。
| 学校の種類 | 月額 |
|---|---|
| 下記以外の支給対象高等学校等(全日制や私立など) | 9,900円 |
| 国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程 | 9,600円 |
| 公立高等学校(定時制)公立中等教育学校の後期課程(定時制) | 2,700円 |
| 公立高等学校(通信制)公立中等教育学校の後期課程(通信制) | 520円 |
| 国立・公立特別支援学校の高等部 | 400円 |
対象者は平成26年4月以降の入学者で、平成25年度までに在学している人は旧制度の公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度を利用できます。
私立高等学校等授業料軽減助成金は授業料を助成する制度
私立高校を対象に自治体で授業料を助成する仕組みで、内容や名称は各自治体によって変わります。ここでは神奈川県の「私立高等学校等生徒学費補助金」を例にします。
入学金補助額:100,000円
3年間の総支給額は244,000円
この助成金制度は、上記で紹介した高等学校等就学支援金と併用できる場合がほとんどです。
育児休業給付金は最大で月給の67%をもらえる
育児休業給付金とは、育児休業する人を経済的に支援するための給付金で、雇用保険を元に支払われます。
育児休業開始日から6カ月(180日)までは月給の67%を支給され、それ以降は育児休業の最終日まで月給の50%の給付金を受け取れます。
給付期間は出産日(産前休業の末日)、産後休業、育児休業の期間を合わせて1年間です。保育所に入所できないなどの特別な理由がある場合は、受給期間を2年(1年6カ月まで延長したし、その時点で条件を満たす場合は再度6カ月の延長が可能)まで延長することができます。※3
こちらのサイトで育児休業給付金をいくらもらえるか、自動計算できるので育児休業を考えている人は参考にしてください。
制度を使って医療費もお得に!大人・小児別のおすすめ制度
ケガをしたり病気にかかったりした場合は医療費が高額になってしまいますよね。そんなときに利用したい制度が高額療養費制度です。また、子どもを対象とした乳幼児医療費助成・子ども医療費助成制度も知っておきたいお得な制度なので合わせて紹介します。
高額療養費制度を利用して超過分を受け取れる!
高額療養費制度とは、月初めから終わりまでにかかった医療費が自己負担額を超えた場合に、超過分の費用をもらえる制度です。年齢や所得によって自己負担の限度額が変わります。
ここでは年収が約400万円で35歳の人の医療費負担例をみてみます。この場合の自己負担の上限額は約80,000円程度(80,100円+(総医療費-267,000円)×1%)です。30万円を医療機関の窓口で支払った場合、上限額を超えた20万円以上が払い戻されます。※4
乳幼児医療費助成・子ども医療費助成は小児を対象とした助成制度
子どもは流行り風邪にかかったり、転んでケガをしたりと何かと病院に行く機会は多いですよね。自治体では子育て家庭を支援するために乳幼児や小児を対象とした医療費助成制度を実施しています。※5
この助成制度は自治体によって内容や名称が変わります。ここでは八王子市を例に乳幼児医療費助成制度・子ども医療費助成制度を紹介します。名称は「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」です。
八王子市の場合は医療費のうちの保険診療の自己負担分が助成され、所得制限はありません。
- 以下の条件を満たす人を対象に実施されています。
- 市内在住の乳幼児(6才になって初めて迎える3月31日まで)
- 国民健康保険または各種社会保険に加入している人
- 生活保護や里親制度を受けていない人
検索するときは「乳幼児医療費助成」または「子ども医療費助成」と地域名で検索すると、その地域の小児を対象とした医療費制度を確認することができます。
- 「乳幼児医療費助成 名古屋市」
- 「子ども医療費助成 高槻市」
身内の不幸があったらもらえるお金!葬儀を行ったら必ず申請すべき給付金
葬祭や埋葬にはなかなか費用がかかりますよね。そんな時に使用したいのが各健康保険の葬祭費や埋葬費を支給する制度です。また、年金受給者が亡くなった時に受け取れる未支給年金給付という給付金もあるんですよ。
それでは身内の不幸があったときにもらえるお金2選を紹介します。
年金をもらっている人が亡くなったら未支給年金給付の申請を!
年金受給者が亡くなったときに、受け取っていない年金分と、亡くなった月の分まで年金を受け取ることができます。未支給年金を受け取ることができるのは、亡くなった人と生計を同じにしていた遺族です。
未支給年金を受け取れるのは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、左記以外の3親等内の親族で、未支給年金を受け取る順位もこの通りです。
葬儀を行ったときにもらえるお金は5万円!
健康保険に加入していると、葬祭費や埋葬料にかかったお金をもらうことができます。葬儀を行った人によって給付内容や名称は変わってきます。※6
| 埋葬料 | 被保険者が亡くなったとき、葬儀を実施した家族に給付されるお金 |
|---|---|
| 埋葬費 | 被保険者が亡くなったとき、葬儀を実施した知人などに給付されるお金 |
| 家族埋葬料 | 被扶養者が亡くなったとき、家族に給付されるお金 |
もらえるお金は埋葬料と家族埋葬料が5万円、埋葬費は実際にかかった金額の5万円以内まで支給されます。
葬祭費の支給額は自治体によって異なり、1~7万円受け取ることができます。
家族が亡くなったときにもらえるお金でも詳しく紹介しています。
カードローンなら最短今日中にお金が手に入る
これまで住宅、育児、医療関連、葬儀などで国からもらえるお金を紹介してきましたが、これらにはもちろん受給条件があり、公正な審査が行われます。
審査を通過できたとしても、申請から実際にお金を受け取れるまでに最大で3ヶ月程度の時間がかかったりとするものもあります。
待ってられない、今すぐお金が必要だという方は、カードローンの利用を検討してみてください。
しかし、まだ闇金と呼ばれる危険な貸金業者が「審査なし」などとうたって違法な金貸しを行っているのも事実です。
ここでは大手銀行グループが展開している、安心して利用できる大手消費者金融カードローンのみを紹介します。それぞれの強みなどを比較して、商品選びの参考にしてみてください。
今すぐお金が必要&バレたくない人におすすめのSMBCモビット
即日融資を希望していて、カードローンの利用が家族や職場などにバレたくないという方は、SMBCモビットをおすすめします。
ここで紹介している大手消費者金融カードローンはどこも審査が早く最短即日審査が可能ですが、SMBCモビットならさらに優先的に審査を開始してもらう方法があります。
インターネットから申し込んだら、すぐにコールセンターに電話をかけましょう。コールセンターの営業時間は9時~21時で、営業時間の終了間際ではその日中の融資が難しくなる可能性があるので注意が必要です。
web完結でカードレスで申し込めば、近くの提携ATMからすぐに現金を引き出すこともできますし、口座に振り込んでもらうことも可能です。ローンカードが欲しい場合でも、郵送ではなく近くのローン契約機を利用すればOK。
また、なによりSMBCモビットの強みとしてお伝えしたいのは、SMBCモビットはweb完結申込の場合は電話連絡なしで審査してもらえるという点です。職場に電話されるとバレるかもしれないので嫌だという方におすすめなのです。
| 条件等 | 内容 |
|---|---|
| 申込年齢 | 20歳以上74歳以下 ※収入が年金のみの方はお申込いただけません |
| 申込要件 | 定期収入があればパート、アルバイトでも可能 |
| 実質年率 | 3.0%〜18.0% |
| カードローンの特徴 | ・申込後、電話連絡すればスピード審査 ・審査は最短30分 ※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります ・web完結なら電話連絡なし |
SMBCモビットはバレ対策に特化!電話連絡・郵送物なしでスピーディ&誰にもバレずにキャッシングできます。
※WEB完結の場合

あと
即日融資も可能で無利息期間が嬉しいプロミス
SMBCコンシューマーファイナンスのプロミスは、本人確認の手続きも非常に簡素化されており、金融機関口座と運転免許証、健康保険証などで確認してくれるので、審査がとてもスピーディ。審査結果は最短30分で通知されます。
もちろんweb完結申込でカードレスも選択できます。
審査に通って契約手続きが済めば、スマホ一台から借り入れが可能です。会員サービスに契約完了時に届くログイン情報でログインして、「瞬フリ」という振込キャッシングサービスを利用すれば、最短10秒で指定した口座にお金を振り込んでくれます。
また初めての利用の場合、最大30日間の無利息期間がサービスされます。この無利息期間を活用すれば利息0円でお金が借りられるのです。
返済の目処がある程度たっていて無利息期間内に完済できるという方は、プロミスでの借入がお得ですね。
| 条件等 | 内容 |
|---|---|
| 申込年齢 | 20歳以上69歳以下 |
| 申込要件 | 主婦でも学生でも仕事をしていて収入があれば利用可能 |
| 実質年率 | 4.5%〜17.8% |
| カードローンの特徴 | ・審査は最短30分 ・WEB完結でカードレス ・即日融資も可能 ・最大30日間の無利息期間 |
お急ぎならプロミス!土日でも夜間でも24時間OK。web契約なら最短3分、誰にもバレずにキャッシングできます。もちろんパート・アルバイト、主婦、学生もOK!
30日間無利息※キャンペーン中
※メールアドレス登録、Web明細利用が必要。

あと
優先審査、原則在籍確認なし、無利息期間が嬉しいアイフル
アイフルも、web申込で最短18分融資も可能なスピーディさが強みです。
どうしても今日中にお金が必要で急いでいる方は、スマホから申し込みをした後、申し込み完了メールが来たらフリーダイヤルに電話をしましょう。優先的に審査をしてもらえます。申し込み時間が9時~21となっていますので、その点だけ注意してください。
アイフルも輸送物なしのカードレスにすることが可能です。
アイフルの何よりの強みといえば、原則在籍確認なしという大手消費者金融カードローンではめずらしい審査方法です。職場への電話連絡が不安な方におすすめです。
アイフルもプロミスと同様に、利用が初めてであれば最大30日間無利息になるサービスがあります。
| 条件等 | 内容 |
|---|---|
| 申込年齢 | 20歳以上69歳以下 |
| 申込要件 | パート・アルバイトでも可能 |
| 実質年率 | 3.0%〜18.0% |
| カードローンの特徴 | ・WEB完結で手続きが簡単 ・原則在籍確認なし ・電話連絡で優先審査 ・30日の無利息期間あり |
WEB申込なら最短18分融資も可能!原則 在籍確認なしで郵送物もなし、誰にもバレずに借りたい人におすすめです。※はじめての方なら最大30日間利息0円。24時間受付中です。
※20~69歳の方が対象です

※提携ATMにて、お取り引きの都度、手数料が発生します。
※アイフル株式会社ATMは手数料がかかりません。
あと
審査は最短20分のアコム
アコムはカードレスで契約できて、審査は他社と同様にスピーディで、無利息期間も最大30日間あるカードローンです。
自動契約機「むじんくん」を利用すれば、その場ですぐに審査結果がわかります。審査を通過したら、カード発行まで自動契約機「むじんくん」でできますので、時間によっては仕事帰りにも利用できるでしょう。
楽天銀行の口座を持っている方なら振り込みが便利です。24時間いつでも振り込みしてもらえます。
| 条件等 | 内容 |
|---|---|
| 申込年齢 | 20歳~72歳 |
| 申込要件 | パート、アルバイトでも安定した収入があれば利用可能 |
| 実質年率 | 3.0%〜18.0% |
| カードローンの特徴 | ・審査は最短20分 ・無利息期間がある ・自動契約機「むじんくん」なら申し込みからカード発行までできる ・楽天銀行なら24時間振込依頼可能 |
アコムは最大30日間金利0円!原則、在籍確認なし(※)で、最短20分融資可なのでお急ぎの人にも大人気!ネットやATMから24時間借入できます。
※ 原則、電話での確認はせずに書面や申告内容での確認を実施

提携CD・ATMの詳細についてはアコムのホームページでご確認下さい。
あと
最短即日融資、無利息期間がながいレイク
レイクは、平日21時(日曜日は18時)までに契約手続きがすめば、当日中に振り込みをしてくれるスピード融資が特徴です。
もちろん郵送物もなしにできますし、スマホひとつで全ての手続きが完了できるのも他のカードローンと同様にメリットですね。
レイクの最も大きな強みは、初めての利用なら「選べる無利息期間」がある点です。WEB申込が条件で、60日間も無利息になる特典があります。
| 条件等 | 内容 |
|---|---|
| 申込年齢 | 20歳以上70歳以下 |
| 申込要件 | パート・アルバイトでも安定した収入があれば可 |
| 実質年率 | 4.5%〜18.0% |
| カードローンの特徴 | ・最短25分融資 ・借入まで全てWEBで完結 ・WEB申込限定60日間無利息 |
もらえるお金はいろいろ!ライフプランに合わせて給付金制度を利用しよう
国や自治体からもらえるお金は、住宅関連や子育て関連、医療関連など、いろいろなものがあります。
給付金と聞くと縁遠いように感じますが、自分にも適用される制度は案外あるものです。ライフプランに沿って、その時々で自分が使える制度がないかチェックしてみましょう。
例えば住宅購入のときは住宅ローン減税、子どもが生まれるときは出産育児一時金、ケガをしたときは高額療養費制度の利用など、制度を上手に使うことで、出費をおさえられます。
ここで紹介した国や自治体などからもらえるお金は生活に役立ち、いざというときに使えるものばかりなので、ぜひ利用してください。